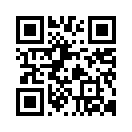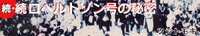2019年01月11日
[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-001.jpg)
謹んで新年のごあいさつを申し上げます
本年もかわらぬご愛顧のほど
お願い申し上げます
ATALASネットワーク
ホームページ | Face Book | ATALAS Blog
ホームページ | Face Book | ATALAS Blog
改めて、新年のごあいさつを済ませたところで、今年もやります。
ATALASネットワーク新春恒例の「新春放談2019」。今年は無謀にも「歴史と文化と民生ITの融合」を目指す初夢チャレンジでのトークライブ(の収録)を実施しました。インフルエンザに罹って参加できなかった江戸之切子(「島の本棚」主幹)も、もしかしたら参加できたかも知れない画期的なシステムを考案したつもりでした。
東京と宮古島をSkypeで結び、Googleドキュメントの音声入力をドッキングさせ、パソコンにすべてを自動筆記させる。という発想までは非常に素晴らしいシステム化だったのですが、年明け前に、若干挫折。いや、完全に挫折・・・・2020年に乞うご期待!
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-002.png) ということで、こんなこともあろうかと準備しておいた、文明の利器たる「ボイスレコーダー」からの音声書き起こしで、今年のテキストライブはお届けします。過年の“万字堅め”には及ばないと思いますが、新年の初笑い(?)としてヲタのしみ下さい。
ということで、こんなこともあろうかと準備しておいた、文明の利器たる「ボイスレコーダー」からの音声書き起こしで、今年のテキストライブはお届けします。過年の“万字堅め”には及ばないと思いますが、新年の初笑い(?)としてヲタのしみ下さい。出演者
【優】 宮国優子:ATALASネットワーク フロントマン&「Ecce HECO.(エッケヘコ)」裏座担当
【片】 片岡慎泰:「Ecce HECO.(エッケヘコ)」一番座担当
【ツ】 ツジトモキ:「続ロベルトソン号の秘密」ライター
【モ】 モリヤダイスケ:「んなま to んきゃーん」ライター&ATALAS Blog編集室
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-003.png) 【優】えー、みなさん。あけましておめでとうございます。
【優】えー、みなさん。あけましておめでとうございます。【All】おめでとうございます。
【優】今年、2019年は平成31年。「平成」が終わることじゃないっすか!。
【モ】昭和で云えば、昭和94年。大正108年。明治152年。そして皇紀2679年ですね。
【優】そーゆーネタはいいから(笑)。でも、“年”というか、時間にまつわるネタから始めましょうか。“年”の初め~のお正月ですから!
【片】平成元年は1989年の1月8日からです。
【ツ】1989年はベルリンの壁崩壊の年です。「天安門事件」もこの年。
【片】ドイツ統一、あ、再統一は1990年です。
【優】うああ。激動の世界ですねぇ~
【モ】平成元年の7月は、宮古空港から羽田への直行便が就航しました。あと、当時の平良市総合博物館(現宮古島市総合博物館)も開館してます。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-034.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-004.png)
【左 うえのドイツ文化村キンダーハウスにあるベルリンの壁】 【右 宮古島市総合博物館】
【優】平成元年はわたしが宮古高校を卒業した年なんですよ。でも、卒業式のあった3月には、まだ博物館は開館してなくて、記念写真を撮りにいきました。「読めば宮古」でかすかにその頃の写真がある。あと、一周道路(県道83号線)で逆立ちとかしてたくらい、車がいなかったですね。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-005.png)
【「読めば宮古」より(ボーターインク刊)。2002年に発売して17年目。なぜか未だに売れているマニアックな宮古本。恐るべし“宮古マジック”】
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-006.gif) 【モ】博物館といえば、パニパニガールズの2ndマキシシングル「シャララ」のジャケット写真にも使われているんです。
【モ】博物館といえば、パニパニガールズの2ndマキシシングル「シャララ」のジャケット写真にも使われているんです。【優】また、ずいぶんマニアックなネタを。。。
【モ】あ、でも、発売は2005年だから、開館当時じゃないね(笑)。
【ツ】周年行事はなんですかね。
【片】今から100年前。1919年は、第1次世界大戦が終結して、パリ講和会議が始まった。その時の様子は、この歌を聴けば判ります。風刺効きすぎですが。
※パリ講和会議(パリこうわかいぎ:Paris Peace Conference)は、1919年1月18日から開会され第一次世界大戦における連合国が中央同盟国の講和条件等について討議した会議。世界各国の首脳が集まり、講和問題だけではなく、国際連盟を含めた新たな国際体制構築についても討議された。
【添田さつき・平和節/土取利行(唄・演奏)】
【ツ】あと、1919年だと、ニコライ・A・ネフスキーが小樽高等商業学校(現・小樽商科大学)に行った(講師として就職した)年ですね。
【優】ネフスキー絡みでは、そのあたりの時代背景がこの回を読むと雰囲気が掴めます。
第8回「下川凹天の弟子 森比呂志の巻 その6」
【モ】絶滅した謎の鳥、“ミヤコショウビン”が新種として認定された年でもありますよ。
【All】(ニヤニヤ)
【片】140年前の1879年は、「サンシー事件」がありました。
【ツ】じゃあ、1929年は日本勧業銀行那覇支店長の松岡益男が、親越の博愛記念碑の拓本を取って、“再発見”した年です。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](https://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/DSC_0003.JPG)
第178回「ドイツ皇帝博愛記念碑 拓本」
【ツ】あと、この年は、ネフスキーがロシア・・・じゃない。ソ連に帰国しています。
【モ】1929・・・昭和4年ですから、『宮古史傳』の慶世村恒任が亡くなってますね。
第1回 「宮古研究乃父 慶世村恒任之碑」
【片】1939年。第二次世界大戦が勃発します。
【優】また、戦争~!
【ツ】では、さっさと戦後にします。1949年。下地町に町制が施行されました。
【モ】前の年に下地村から上野村が分村したのに、町制が出来るほど人口があったというのが凄いと思う。
【ツ】ちなみに、1937年に平良市が市制(町制は1924年)、城辺町が町制をそれぞれ施行しています。
【モ】1959年は第一宮古島台風こと、“サラ台風”の年ですね。ついでに、“コラ”(第二)が1966年、“デラ”(第三)が1968年です。
1966年。台風コラと台湾のサーカス団のお話。「フォルモッサタイフーンサーカス」 from 一柳亮太
【片】復帰前後の1969年は下里公設市場ができた年ですね。
【モ】それ、少し違いますね。下里の市場(南市場)は明治末期、下里村番所跡(1908年に平良村の最初の村役場が置かれた場所)に市場が開場されます。戦禍によって失われ、戦後に再建されますが、1967年の火災によって消失。米軍政府の援助によって1969年に再建(先代の市場)されます。この市場も2008年には老朽化から閉鎖取り壊しとなり、2011年に現在の市場がリニューアルオープンします。
【ツ】1972年が本土復帰です。この年に博愛記念百年祭が催されました。ですが、ロベルトソン号の遭難は1873年、博愛記念碑の建碑は1876年、建碑60周年祭も1936年ですから、キリとしてはかなり微妙。復帰記念事業の一環だったかもしれません。この百年祭では「ドイツ皇帝博愛記念碑」のレプリカが、カママ嶺に建立されました。
第2回「ドイツ皇帝博愛記念碑 レプリカ」
【片】復帰の翌年(1973年)に、下川凹天が千葉の野田で亡くなります。
Ecce HECO.(エッケヘコ) 第1話「巨星、墜つ。」
【優】1975年に沖縄国際海洋博(EXPO’75)が本島北部の本部町で開催されました。今の美ら海水族館のあるトコですね。わたし、コレ、見に行きました!。覚えているのはお弁当とアクアポリスだけだけど。魚の群と言うか、魚の渦を見た。
【モ】最近は少なくなったけど、海洋博の100円硬貨が県内ではまだ流通してて、極まれにお釣りに混じってますね(笑)。
【ツ】このアクアポリスは老朽化が激しくなり、最終的に2000年に屑鉄として売却されてしまうんですよね。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-007.jpg)
【1975年 沖縄国際海洋博覧会 日本政府出展 海上施設「アクアポリス」 (1re1@1re1)】
【モ】1976年に宮古でもNHKのテレビが見られるようになります(ラジオは1972年)。実際には復帰前からRBC(琉球放送、1958年にラジオ、1960年にテレビが放送開始)やOTV(沖縄テレビ、1959年放送開始)がCMをつけて、NHKの番組を放送している時期がありました。1967年に沖縄の公共放送としてNHKの全面支援で沖縄放送協会(OHK)が設立され、県内で最初に宮古島でテレビ放送が開始されました(本島1年、八重山より1日早い)。この時、のど自慢の宮古島予選会が北小のグラウンドで開催され、その模様が公開放送されました(現存する宮古で二番目に古い映像。一番は1936年の建碑60周年祭の様子 宮古島最古の映像に関する一考察)。
OHKは復帰後はNHKへと統合されますが、民放もNHKも離島県ならではの苦労話というか、面白い話がいっぱいあるのですが、話し出すと長くなるので今日のところはやめておきます。
島の小さな大きい放送局<上> from 一柳亮太
島の小さな大きい放送局<下> from 一柳亮太
第31回「沖縄放送協会 宮古放送局
第68回「友利實功氏生誕地」
※1960年(昭和35年)に琉球放送ラジオ番組、素人のど自慢大会で「なりやまあやぐ」を初めて歌い世に出した。また、記事でNHKのど自慢の話にも言及しています。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-008.jpg)
【1967年12月22日 先島テレビ局開局(沖縄公文書館)】
【モ】あ、そうそう。あと、宮古テレビが1978年に開局してます。
【ツ】1978年といえば、沖縄は“ナナサンマル”ですね(沖縄の交通法規変更)。
ナナサンマルを追え! [んなま to んきゃーん] SP
【モ】1980年、伊良部町制施行。1982年、第1回全日本トライアスロン宮古島大会開催。
【優】節目ではないけど、これはイロイロ、怒濤の変貌ですね。いつも言ってますが、まさに、“裸足からナイキ”って感覚!。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-012.jpg) 【モ】あ、忘れてました。1979年。下地島空港(現在は“みやこ下地島空港”と愛称がつきました)が開港してます。当時はパイロット訓練施設が主でしたけど。
【モ】あ、忘れてました。1979年。下地島空港(現在は“みやこ下地島空港”と愛称がつきました)が開港してます。当時はパイロット訓練施設が主でしたけど。【優】下地空港、40周年かぁ!。
【モ】下地空港じゃなくて、下地“島”空港ね(笑)。よく言い間違えてる人が多いのですよ~!。
【優】あははっ。今年の春だっけ。ターミナルビル作って、LCCが就航して、いずれ国際便も来るみたいだし、大きく変わるよね。
【モ】ですね。成田-下地島に、ジェットスターが就航します。就航記念セールで「385円」とかって、とんでもない価格設定にあちこちで踊らされてましたよ(笑)。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-013.png)
【片】えー、次は1989年かな。これでいよいよ平成元年。
【モ】さっきも出しましたけど、羽田-宮古の直行便が就航しました。当時はまだ南西航空時代。日本トランスオーシャン航空(JTA)になるのは、1993年から。ちなみに現在の宮古空港のターミナルは1997年に供用開始。“花笠空港”の愛称で親しまれた旧ターミナルは、1999年に解体されました。
【ツ】1999年は平良市で「第13回柳田國男ゆかりサミット」が開催されてますね。これは全国にある柳田國男のゆかりの地を巡って開催されていたイベントですが、今も開催されているのでしょうかね?。ネットにもこのイベントの情報はほとんど載ってないんですよ(ご存知の方、情報をお寄せください)。
【モ】柳田國男といえば、宮古島市中央公民館に柳田の長男・為正が寄贈した「柳田為正文庫」という施設があるのですが、文庫(図書室)としては活用されていないらしいんですよ。今年7月には新図書館(未来創造センター)も完成するわけですから、こういうのもなんかとフォローして欲しいですね(公民館図書室と市立図書館では、設立経緯異なるためどうなるのかは不明)
【優】10年前。2009年は?。
【片】第2代宮古島市下地敏彦市長が就任しました。
【モ】あ、そうか~。もう10年やってるんですね。2005年に1市3町1村が合併して宮古島市になりましたけど、その時の市長職務執行者って知ってます?(笑)。
【優】市長職務執行者?
【モ】5市町村が合併したので新しい市長を選ぶまでの間、市長の代理として行政運営を担う人のこと。つまり、一番最初に、宮古島市の市長室で仕事した人。まあ、元の平良市長室だから、新品じゃないけどね。
【ツ】だいたいこういうのは、普通。首長経験者ですね。
【片】これは難しい。。。
【優】知ってる。川田正一!。だって同級生のお父さんだも〜ん。
【モ】正解!。最後の上野村長です。
【優】あの頃は、宮古の首長全員で東京出張するくらいワサワサしてた。あと、新しい市の名前を、宮古市にするか、宮古島市にするか、とかで揺れてたりしてました。
【モ】川田元村長は、面白いところに目をつけましたよね。市長にはこの先、何人もなる人はいるでしょうけど、この市長職務執行者は新市合併の時くらいしかできないので、ある意味、一番最初に宮古島市庁舎の市長のイスに座った人です(笑)。まあ、もっとも元平良市庁舎なので、そのイスは中古品だったのではないかと思いますけどね。(笑)。
重責にも笑顔絶やさず 宮古島市市長職務執行者に就任した 川田正一さん(宮古毎日新聞)
【優】はからずも勢いだけで、10年刻みの“周年”を振り返る形になりましたが、なかなか面白くて。
【モ】調子に乗り過ぎました(笑)。
【優】まあ、ツカミのつもりだったのですが、なんだか宮古島の歴史を振り返る楽しさも語れたのではないかと思いましたし、尺もかなりできたので、これはこれで良いということにします。
後半は、もう少し、マジメにやってみましょうか。。。
※ ※ ※ ※
【優】さっきも言いましたが、わたし、平成元年に宮古高校を卒業したんだよね。これでなんだか一区切りな気がします。30周年です。宮古はこの30年でまさに「世変わり」しました。産業構造がガラッと変わっている。県全体を見てもそう。宮古はその余波が数年後から起こったように思います。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-014.jpg)
【優】こちら。ついでになるけど、あの頃の観光客数は、こんな感じ。ネットでググりまくって、やっと出た画像です(笑)。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-015.png) 【モ】“裸足からナイキ”ってのがなんか判るようなグラフだね~。
【モ】“裸足からナイキ”ってのがなんか判るようなグラフだね~。【優】わたしたちが産まれた時は、1971年で復帰前だからか3〜4万人くらいみたいです。宮古空港は1984年に宮古空港ジェット化して少し増えたんだと思います。そこまでは資料がないので、よく判らないけど。
【ツ】なるほど。人の動きが活発になって来たということですね。
【優】島を出た時が平成元年。1989年は15万人程度でしょうね。多分、来年には150万人近くなる。10倍です。よくわかる伸び率です。
【優】もうひとつ、こんなの。40万人達成までは伸びは小さかったし、石垣、本島にくらべ好調といえるほどでもなかったです。時代がやっと宮古に焦点があたるようになった。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-016.jpg)
【優】沖縄県の資料だと、第5次沖縄県観光振興基本計画改定版(平成29年3月改定)では、宮古はこのように追記されています(太字囲み)。いずれ、文化発信、文化保存をしていくリテラシー養成機関がいずれ必要になるように思うんですよね。そこに、人にお金をかけてほしい。今は、まだ箱物の段階だけど。
第5次沖縄県観光振興基本計画新旧対照表 (pdf)
宮古圏域の空港(宮古空港・下地島空港)については、空港施設の整備を図ることにより、国際線の受入機能を強化するほか、国内外への路線拡充に向けた取り組みを促進する。
さらに、平良港については、国際クルーズ拠点を形成するため、官民連携によって14万トンクラスのクルーズ船の受入れに向けたハード・ソフト両面の取り組みを進める。
併せて、国内外からの観光客の増大に対応するため、観光地形成促進地域制度を活用した民間施設の整備促進、通訳案内サービスの向上などの受入体制の強化に取り組み、観光客の満足度向上に努める。
また、自然、文化等多様な魅力を有する離島地域を観光資源として積極的に活用するため、離島の多様で特色ある魅力を発信し、各離島への誘客を図るとともに、離島を含む広域周遊ルートの形成や受入環境の整備に関係機関と連携して取り組みます。
【優】沖縄県や宮古島市は良い資料をネット上に上げているから、キーワードを検索するとワラワラ出てきます。そういうのが広く市民に浸透すると良いよね。今後ますます栄えるツーリズムに関してマーケット分析や方向性を住民主導で決定するのに最適。お役所言葉も多いから読みにくいけど、暇な時に見てほしいなぁ。島の行政は文句ばかり言われてるけど、頑張ってもいるよ。他に例がないような宮古島という立地と環境で、一生懸命頑張っていると思うよ。産業構造も第1次だけではなく、第6次まで広がってきているし。
【モ】ごめん。第4次、第5次、第6次産業ってなに?。第1次は農林水産業。第2次は製造業。第3次は流通やサービス業みたいなことは学校で習った気がするけど。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-017.jpg)
【片】第4次産業。政府、調査機関、文化団体、教育組織、図書館など、社会における知的組織。第4次産業は、第1次産業から第3次産業の定義に入らない新しいタイプのもので、情報通信・医療・教育サービスなどの知識集約型。技術開発など、物質やエネルギーの大量変化(消費)を伴わないという特徴があります。
続いて第5次産業。 第5次産業とは、 第1次から第4次までの産業形態を自由に融合、分化させて、これまでになかった一種の不定形な産業を生み出す産業。第4次産業に関連した産業分類で、NPO団体、メディア、芸術、文化、高等教育、ヘルスケア、それと科学技術や政府などの上級管理職など。ソフトウエア産業とか、情報通信産業、技術開発など、物質やエネルギーなどの大量消費を伴わない産業。 マスコミや芸能界なども含まれるようです。
【香川県三豊市HPより】
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-018.png) この絵は、1次×2次×3次で6次を表しています。第1次産業を従来の生産だけでなく、2次の加工、3次の流通まで一貫して行うことで高次化した産業のこと。
この絵は、1次×2次×3次で6次を表しています。第1次産業を従来の生産だけでなく、2次の加工、3次の流通まで一貫して行うことで高次化した産業のこと。第6次産業とは、農業や水産業などの第1次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を表す、農業経済学者の今村奈良臣が提唱した造語でした。また、このような経営の多角化を6次産業化と呼んでいるようです。ちなみに、6番目という意味ではありません。6次産業という名称は、農業本来の第1次産業だけでなく、他の第2次・第3次産業を取り込むことから、第1次産業の1と第2次産業の2、第3次産業の3を足し算すると「6」になることをもじった造語だったのですが、現在は、第1次産業である農業が衰退しては成り立たないこと、各産業の単なる足し算ではなく、有機的・総合的結合を図るとして掛け算であると今村奈良臣が再提唱しています。付加価値として、農業のブランド化、消費者への直接販売、レストランの経営などが挙げられる。第1次産業に付加価値をつけて高度化を目指すという観点では、第1.5次産業に類似していますが、第6次産業は加工、流通を複合化させるという視点が、一層明確です。今後、各次の産業の連携による農村の活性化や、農業経営体の経営多角化のキーワードとして使われていくんでしょうね。
【優】ご説明ありがとうございます。現段階では、法規制やノウハウの壁があって、それ以前に、第1次産業への参入障壁はまだまだ高いですよね。しかし、現市長が第1次産業については重要視した所信表明していたことからもわかるように、宮古の場合、離島ということが、逆に利点になって、いずれ第6次産業に結びつくんだと思います。将来、エレクトロニクス業界が、EMS(electronics manufacturing service)を活用するようになれば「第n次産業」という分類に大きな意味がなくなる、とも言われています。
【片】島の中の人だけでなく、取り巻く人々が増加傾向にあるってことは、産業が、より宮古独特のものになるということなのかもしれない。
【優】じゃあ、宮古に来る人はどんな人が多いかなんだけどね。ネットで発表されているような調査報告から見えてくることもある。使いようによっては、自分の仕事に生かせると思うんだよね。特に宮古での個人事業主の人とか。新しい職業とか出てきそう。
この資料からわかることは
・関東の女性30代がリピーターになってるぽい、とか。
・ファミリーより、夫婦、カップルが多い、とか。
・半数がリゾートホテルに泊まって、観光地巡りをしてる、とか。
でも、多分、観光客も知っているんですよ。表面的なリゾート以外の何か面白いものが宮古にはあるって。だからリピータ率が高い。そして、人の紹介が多いってこともわかる。誘われて、っていう人が多い。
関係ないような話かもしれないけど、この年末、なぜかカフェで宮古島の話に白熱してる人に3回ほど出くわした。「宮古島出身です!ありがと!」と言いたくなったけど、一応知らない人なのでやめときましたが。彼らの島を語る熱が半端なかった。人が人を呼ぶかんじは、実は昔から脈々とあるんじゃないでしょうか?
【モ】難しい単語はよく理解できないけど、個人的な感覚とかイメージだけど、少し前は、自分で手配して自分のスタイルの旅で島に来る“旅人”は、鼻を利かせて面白いものを探して旅をしてきた。その一方で、パックやセットのフツーな“旅行者”。特に団体客とかには、そーゆーのはあまりなくて、なんとなくみんなと一緒に連れて来られて、勧められるままに観光して、「あ~キレイ」そんな感じがしてたけど、インターネットの登場で情報の拡散と収集の量が急速に、しかも格段に増えた。つまり、情報と選択肢が増えて誰もがイロイロ知ることができるようになってきたから、“旅行者”が“旅人”のスタイルに近づいて来た。
“旅人”側からすると、なんか急に人増えた(笑)。その結果として荒れてしまうこともあるけど、深い、ディープミャークを楽しんで、ファンになってくれる人が増えるのは、宮古島のファンとしては嬉しい。あ、そうか。。。人がいっぱい来るようなったから、俺、より深いとこに向かうようになったのかなぁ・・・自己完結した(笑)。
【ツ】だから、穴なんですね~!(笑)
【優】もしも、わたしが大金持ちだったら、宮古インフルエンサーにお金を払って、優遇します(笑)。島に住む宝ですよ、こういう人たち。そしていろんな企画を打ってもらう。その人たちが呼びたい人と何かコラボできる、島の人も楽しめる企画がある島にする。リゾートもいいけど、それだけじゃないということを体現してもらえる仕組みを作る。この統計のリピーターの数から行くと、実際にそういう人がいる証拠だし、将来的にポテンシャル高い人材も確実にいる。昔は、島に仕事がないから若者は出ていったけど、今は島を軸足に生きていけるような若い人たちも増えると思う。この人たちが自由に島遊びを教えてくれるように暇をつくってもらうためにも、将来的に歴史、文化、自然を愛する宮古島ファンがスポンサーのなってくれるといいね。
宮古圏域の圏域外客(県外客・圏域外県内客)マーケットと観光消費単価に関する分析(pdf)
【優】少し、話を戻すんだけど、現市長はある種、土建的な市長として、常々賛否両論で言われていますよね。でも、土建的市長と言えば、このひと。下地米一市長を忘れてはなりませんね。宮古の平成のスタートを華々しく切った。1986(昭和61)年7月に市長に就任して半年後には、地下ダムの予算獲得して、東京直行便就航にも尽力した。この流れがあるから、島の開発に対しては島民それぞれ思うことがあるんじゃないかな。簡単に賛成とか反対とか決められない。
米一市長は、1987(昭和62)年3月に、初代沖縄開発庁長官山中貞則、を宮古に招いたのをはじめ、当時の沖縄開発庁長官綿貫民輔、沖縄県知事の西銘順治らを視察させ説得に動いた。宮古からの要請団が運輸省や政治家に向けて東京でPRした。その二年後に東京直行便は就航する。
その後、宮古島市(2005年)が出来るんだけど、その時の概要はこんな感じです。みんな、その先のことを考えながら、5市町村の首長は「宮古の未来」を考えたんだと思う。先人たちに感謝ですよ。宮古の政治も民衆もギリギリのなかを是々非々で動いている。サーフィンしてるみたいに。宮古が合併を選択したのは、住民の生活圏が一体化していること、住民のニーズの広域化・高度化、少子老齢化、財政状況、住民の理解などとあるけど、データを読むと、最後に書いた財政状況の問題が一番大きいみたい。1市3町1村が合併することによって、特例区などを作れるよう地方交付金なども大幅に上がったことで、拡充したサービスも多いです。
宮古島市合併要覧(pdf)
この表を見ると、淡々と書いているけど、2の「合併関係市町村の基礎情報」とかは、当時の市町村の様子がよく分かる。城辺町の高齢化はすさまじかった、とか。三役はみんな失職とか。島の規模だと、個人的に中傷されることも多く、いわゆる首長関連の人たちは胃が痛かったと思う。ところが、その後は、この合併要覧であるような議員の任期や定数、役人の数もさほど減っていないし、箱モノ行政から脱却しにくい構造にある。雇用を生んでいるから仕方ないとも言えるけど。「宮古の未来」を考えて動いていたそれぞれの首長達は、今もいろいろ考えているんじゃないかな。そして、今の市長だってやれることはやっているんだと思うんですよ。
【片】宮古は、過渡期なんだろうね。ポテンシャルが高いのに、今の状況はもったいない。
【優】そうですね。観光客、移住者の人も増えたけど、こういうバックグラウンドが宮古にあったんだし、今のものさしだけで宮古のひとを見てほしくないなぁと思ってます。今回の辺野古県民投票のことでもやっぱり宮古は・・・って喧々諤々なので。人は記憶やかつての感情とともに行動していると思うんですよ。だから、いろんな意見があるし、それこそ善悪では片付けられない。今回は、そんなことをふまえて宮古的にそんなリメンバー的なこと(笑)を振り返りたかった。
【ツ】その間、宮古島を訪れた要人としては、2004年の天皇皇后両陛下の行幸啓がありました。また、2000年の九州・沖縄サミットで沖縄を訪れた、当時のドイツ首相シュレーダーがうえのドイツ村を訪問します。あと、少し古い話になりますが1965年には、佐藤栄作首相がやって来ます。
ご視察(ティダファームたらま) 平成16年1月25日(日) 宮内庁
第53回「下地町役場」
※行幸の際に昼食を召し上がり、陛下が宮古島の情景を詠んだ句碑があります。
第55回「上野村村制50周年記念碑」
※行幸の途中で休息された上野役場。記念碑が建立されています
第102回 「お通りオトーリ」
※シュレーダー首相の来島を記念して、空港からドイツ村までの道をシュレーダー通りと名づけた
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-019.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-020.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-021.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-023.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-022.jpg)
【上 来宮した佐藤首相の演説@宮古空港】 【中左 佐藤首相を見に集まった観衆】 【中右 モクマオウに登っている人たち】 【下左 佐藤首相の車列に沿道から旗を振る人たち】 【下右 市役所(先代)に到着した一行。道向かいは琉球政府(現在の第二庁舎)】(沖縄公文書館収蔵「写真が語る沖縄」より)
【モ】佐藤栄作は宮古から上京した“豆記者”から「島にテレビを」と請願され、復帰前の沖縄訪問時に宮古島へもやって来て、その後、OHK(沖縄放送協会。復帰後にNHKへ合流)によるテレビ放映などが始まりますからね。
【片】ほほーっ、なかなか面白い。
【モ】首相演説は宮古空港。まだ花笠ターミナルすらない頃。モクマオウの木に登ってまで観覧してます。琉球銀行が見えるので西里通りだと思うけど、まだ交通法規が逆なのはともかくとして、この頃はまだ西里通りが対面通行だった頃かと(お店の並びから市場通りかもしれない…正確な情報を求む)。歓迎の門があるのは当時の平良市役所前。マクラム通りを挟んだ向かい側(左手が平良港)は現在の第二庁舎(旧琉球政府庁舎)で、今も同じ建物が立っていますね。(GoogleMAP)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-024.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-026.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-025.jpg)
【左 港向けマクラム通り。左は琉米会館右は北小】 【中 先代の平良市役所】 【左 琉球政府(現在の第二庁舎)】(沖縄公文書館収蔵「写真が語る沖縄」より)
【優】えー、ネタ・・・じゃない。話は尽きませんが、そろそろシメに入りましょうか。みなさんの来年の目標は?
【片】「宮古未来塾!」
【東京組】(爆笑)
【モ】なんすか、それ?
【優】みんなで、未来を見据えつつ学びましょう、ってことじゃないすかね(笑)。
【ツ】今年は、ガッツリ世界的視野からロベルソン号の論文を書いて、また科研費もとります!。
【モ】オトナの自由研究と云い放っている「んなま to んきゃーん」の連載が、昨年おかげさまで200回越えまして、まだ続くのかと生暖かい目で見られていますが、最近はマイナーな井戸ネタばかりになっていますが、たぶん、もう少し続きます(笑)。なので、完全に個人的なコトですが、今年はなんとか「井戸本」の同人誌を制作して、「みゃーけっと」で異彩を放ってみることを目標にしてみます。
あと、ATALASネットワーク的には、大きくて刺激的な活動はどうしても、優子さんのいる東京組の方が派手なのですが、ATALAS宮古としても、歴史や文化の側面からアプローチした活動を盛り上げたいです(ATALAS倶楽部)。
たとえば、宮古の歴史の一部分にスポットをあてて、それとなく紐解くようなミニミニ勉強会と云う名の井戸端会議とか、古写真とか古地図、古電話帳を眺めて、あれやこれやと時代を探って、可能なら現地まで見に行くような寄合とか、ぶらぶらカメラ片手に路地裏を探検して宮古っぽいモノを探して歩くツアーとか。説明が下手過ぎて伝わらないかもしれないけど、やってみたらそこそこ面白いと思う気がしてるんだけど、需要がなかなかないかもしれない。けど、いっしょに盛り上がって楽しんでくれる人々を熱望しています(笑)。
【優】こちらは、歴史と文化を学ぶ成功モデルがデジタルとアナログで構築できないかなとは思っています。東京の個人事務所的なTandyをもう少し組織的に動かしたい。あ、でも、組織一丸とかは苦手なので、各人が楽しく、ゆるやかに、ゴーゴーって感じです。
で、しょっぱなの1月は、ボーダーインクの新城和博さんのトークイベントがあります。
新城和博『ぼくの沖縄復帰後史プラス』刊行記念スペシャルトーク(2019年1月15日@大岡山)
2月からは、宮古島から始まる本を出した谷川ゆにさんや、石垣島関連で本を出版された姜信子さんたちとのコラボも考えています。題して「野生会議99(仮称)」を妄想中。実は、新城さんのこの本の書評を書いたことがある姜さん。ほんと、世界は狭い。
谷川さんは、谷川健一の姪っ子さん。なぜか、宮古に行って「宮国優子に会え!」と言われて大岡山に来てくれた。まじで、小学校の同級生気分で盛り上がってます、はい。
それにビジュアルフォークロアの北村さんや法政大学の福寛美先生、民俗学者の酒井卯作先生、法政大学の名誉教授になられた元沖縄文化研究所の屋嘉先生、与論島出身の作家の喜山荘一さん、奄美出身の古勝監督など「琉球弧に関わること」を楽しめる一年にしたいです。
うぅ、他にもいますが書ききれないです。あくまで個人的な妄想なので、これから交渉しますけど、笑。宮古に連れてく人も増えそうです。
もちろん、誰でもなにかやりたいってことがあれば、じゃんじゃん連絡もほしいですね。
誰か、YouTuberとかなってくれないかなぁ(笑)。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-027.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-028.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-029.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-030.jpg)
【優】それから・・・年末にふってわいた宮古馬関連も少し動きが出てきそうです。あまりにも個人的な問い合わせがハンパなかったので考えています。わたしたちでできることをなので、勉強会とか聞き取りとか、裏支えかもしれませんが、宮古馬に関する東京での資料提供とかおしゃべりとかですね。基本的に運動母体にはなるつもりはありません。宮古の歴史と文化を知らずして、ドカドカと熱狂的に動物愛護を掲げても、早晩頓挫すると思うので、できるだけそんなことがないように、という気持ちです。対話の地ならし的なもののお手伝いですかね。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-031.png) 個人的には、琉球競馬を再考した梅崎晴光さんや、「スケッチ・オブ・ミャーク」の久保田麻琴さん、神奈川フィルハーモニー管弦楽団のチェリストの長南牧人さんなどなど、いろんなご連絡を個人的に頂いています。まだ打ち合わせもしていないけど、やれることは相談しながらですね。宮古で中心になっている皆さんの余計な邪魔はしたくないです。
個人的には、琉球競馬を再考した梅崎晴光さんや、「スケッチ・オブ・ミャーク」の久保田麻琴さん、神奈川フィルハーモニー管弦楽団のチェリストの長南牧人さんなどなど、いろんなご連絡を個人的に頂いています。まだ打ち合わせもしていないけど、やれることは相談しながらですね。宮古で中心になっている皆さんの余計な邪魔はしたくないです。【優】同時に、わたしたち「ATALASネットワーク」では、歴史と文化の側面から、東京という離れた土地で、どうやって島に向けて支援することができるかを考えて動いています。そうした取り組みのなかから生まれてきたものとかつながってきたことを大事にできればなぁ、と。宮古島出身の平良くんたちが動き始めた。この広がりも少しご紹介します。
【県外で活躍するウチナーンチュのストーリーを届ける「東京都沖縄区」】
【優】個人的には「あー、宮古にこういう人も出てきた!」という感じで宮古を楽しんでいます。会いたい人がいっぱいいます、宮古は!
次にご紹介する世代は宮古ニューウェーブかなー。ただの商売とか活動って感じではなく、宮古的真心というか、そんな感じを受けます。それって、別に宮古出身者かどうかとか関係なくて、コラボの様子が広がっているように思うんです。こういうことを同時多発的にできれば、わたしたちは宮古から始めたけど、より広く、より深く、どこでも宮古的要素が広がっていくんではないかな、と。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-032.jpg)
SNSとかネットがここまで、発達しなかったら出会えなかったような人、起こらなかったようなことが、どんどん化学反応を起こしていく。裸足からナイキだったけど、ここからは、タケコプターか(笑)。
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-033-s.jpg) 「ニンギン商店」(※記事の場所から現在は数件隣りの2階に移転しました)
「ニンギン商店」(※記事の場所から現在は数件隣りの2階に移転しました)「Mya-hk LAB.」(Facebook)
ここだけの話、着々と東京⇔宮古でしかけていることもあります。それは本決まりになってから、またお知らせします。発案者のみなさんは宮古の底力って感じで、めちゃくちゃ楽しみ。
あと、片岡、ツジの両先生には、論文の執筆と今まで通りの“宮古ホリック”を貫いていただきたい所存です(笑)。
で。お待たせしている例のヤツ。3月頃には、やっと『凹天本』を出版することができそうですし・・・(笑)。小中学生でも分かる本を作っていますが、資料がなさすぎて、事実確認できず、また資料を探して、書き直しての繰り返しでした。片岡先生、おつかれさまです。で、ここに「島を旅立つ君たちへ」のデザイナーの野口さん、宮古出身のイラストレーター長崎祐子が尽力してくれてます。4月から朝ドラでは、その当時の漫画家たちに焦点があたります。バカ売れしないかなぁ(笑)。
「ぷからす(楽しい)の種」を個々が増やしていくように、互いが助け合うこと。それが「あららがま」の真髄だと思うのです。そのためには、元気じゃなきゃね!。今年も一年、健康に気をつけて、大いに楽しみましょう!
ってことで、
レッツ あららがま 2019 !!!!!
※今回の「新春放談2019」に登場した出来事を、簡単に年表にしてみました。
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│金曜特集 特別編


![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-009.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-011.jpg)
![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-010.jpg)