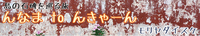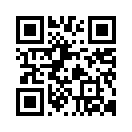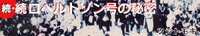2017年01月10日
第117回 「殉国慰霊之碑」
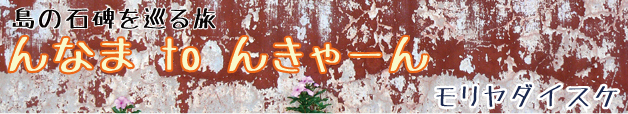
今回ご紹介するのは成川集落で見つけた戦争慰霊碑です。近年、成川の集落を縦貫する道路が拡幅され(全通はまだしていない)、今まで気づかなかった石碑を見つけました(正確には1年くらい前ですが)。台座周辺が綺麗に作り直れているので、拡幅前は道の脇で雑木林の中にひっそりと眠っていのかもしれません。

土地柄、あちらこちらに戦跡があり、慰霊碑も建立されています(主なものは二重越(MAP)に集積されています)。
この「んなま to んきゃーん」でもいくつか戦争関連の石碑を取り上げていますが、重要な歴史の一部ではあるものの、決して華やかなものではないので、微妙に取り扱いが難しいところでもありますが(芸風が軽いせいもある)、めげずにちまちまと差し込んでゆきますのでよろしくございます。
さて、こちらの慰霊碑。碑面に書かれている文言を読んで、ちょっとびっくりさせられました。
とあるのです。船舶工兵第二十三連隊」
殉国慰霊之碑
昭和六十二年八月
長崎市田浦敬久建立
これを読んで、なにが問題かと云いますと、宮古島に駐屯した日本軍は島をいくつかの地域分けして、それぞれに守備する部隊を配置しました。この成川付近は北地区と呼称され、添道に本部を置く独立混成第59旅団(当初は伊良部島に駐屯するも、支隊を残し宮古島に転封)と、細竹に本部を置く歩兵30連隊が担当する区域になりました。
ところが、この船舶工兵第二十三連隊という名は、これまで一度も聴いたことがありませんでした(概ね旅団の隷下にある各部隊は、同一の部隊番号と同じになることも理由です)。
そもそも船舶工兵なるものにもピンときませんでしたので、少し調べてみると、兵種に船舶とはついているものの管轄は陸軍で、いうなれば独自の船で海を行く陸軍といったところ。ちなみに海軍には陸戦隊(基本は基地や司令部、港湾を守備警備する部隊だが、防空防衛の任務を帯びた高射砲兵部隊や、揚陸艇などによる上陸作戦を行う兵団もあった)というのもあったので、どっちもどっち。陸軍と海軍の仲が悪いという証拠のような兵種です。
しかし、この船舶工兵第二十三連隊。そもそもは本島に配置され、海上輸送を担当する部隊なのですが、沖縄線末期は制空権制海権ともに連合軍が抑えており(逆上陸作戦を試みるも敗退した)、乗る船もないため陸戦部隊として前線に投入され、南部の与那原は雨乞森(マリンタウンゴルフ場の北側)付近で、首里城(第三十二軍の司令部)を背後から攻めようと上陸してくる連合軍と戦闘になり、最終的にはほぼ全滅してしまったようです。
「沖縄戦史~公刊戦史を写真と地図で探る~」
首里東部戦線の崩壊(オススメ)
「ああ沖縄 月形から沖縄まで3000km」
スパイ・見れば日本人・山中の電線を切断
では、なぜ宮古島に船舶工兵第二十三連隊が?ということになります。
国立公文書館アジア歴史資料センターの戦史資料を漁っていたら、面白い記述を見つけました(ただ、タイトルと内容に差があり、タイプミスと思われる誤記があったので、修正を加えて読みやすく校正を試みました)。
「戦闘資料調査ノ件 船舶工兵第二十三連隊第一中隊 肥田木隊」まず、これが第二十三連隊の第一中隊の中の肥田木小隊の記録であるということです。小隊ですと4~50人、中隊で160~200人規模(4小隊程度)ですから、かなり小さい規模の部隊の情報ではあります(うた4名が戦死されているようです。第二十三聯隊は奄美にも支隊だしており、こちらも本島とは異なる結果になった)。
資料作成年月日 昭和21(1946)年1月9日
レファレンスコード C11110012700
(一) 部隊名及部隊履歴ノ概要
部隊名 船舶工兵 第二十三連隊 第一中隊
昭和19年6月23日 和歌山ニテ編成
昭和19年7月1日 内地港湾出発
昭和19年7月14日 沖縄本島着
同日 第一中隊 宮古島派遣ノタメ出発
昭和19年7月19日 宮古島着 同日ヨリ
昭和19年8月22日間 揚陸作業ニ従事
昭和19年8月22日 肥田木少隊 石垣島揚陸作業援助ノタメ出発
昭和19年9月23日 石垣島着 同日ヨリ
昭二20年8月15日間 海上輸送業務ニ従事
部隊長 陸軍少佐 大島詰男
(二)指揮隷属関係及其ノ変遷ノ概要
船舶第七輸送司令部→第三十二軍指揮下→台湾軍指揮下
(三)参加セル主要ナル作戦(戦斗)ノ概要死傷、損耗 沖縄作戦
戦傷死 4名
時系列を改めて追ってみると、昭和19年の6月に和歌山で連隊が編成されて、7月には沖縄に到着。すぐに第一中隊だけが宮古島へ派遣されます。そして宮古島でおよそひと月の間、揚陸作業を行っています。物資の荷揚げだけなのか、海上輸送も行っていたのかは定か詳細な内容は不明ですが、一説には物資が豊富で員数の少ない海軍と、物資が少なく員数の多い陸軍というアンバランスな島の駐屯具合だったようです。そして8月になると、第一中隊の一部である肥田木小隊は石垣島へ派遣され、そのまま終戦まで駐留をしていました。
内閣府沖縄振興局 沖縄戦関係資料閲覧室で公文書検索したところ、「船舶工兵第23連隊史実資料」というものを見つけましたが、こちらは和歌山から沖縄に移動し、宮古島派遣を送り出した後は、本隊の顛末が書かれているだけで、宮古に派遣された第一中隊について記された資料を見つけることができませんでした。
尚、「船舶工兵第23連隊史実資料」の最後の行には、「生存者は突撃に参加」という話で締めくくられていました(先の与那原界隈の戦闘で、指揮官が死傷し残存兵もわずかとなっていた)。
最終的に石垣も含め、宮古に派遣された第二十三連隊は、本来の指揮系統の沖縄守備の第三十二軍が連合軍の上陸、軍組織の壊滅により途絶状態となったため、台湾の第一〇方面軍隷下に編入され、戦闘の継続をすることになりますが(これは宮古島の第二十八師団など、石垣島に駐留するすべての駐留軍に対して行われた)、中隊以下の規模なので資料にはほぼ掲載されていません。
陸軍部隊最終位置 大本営直属 第10方面軍 (三十二軍から所属が移動になった部隊名は注記あり)
内閣府沖縄振興局 沖縄戦関係資料閲覧室 第32軍部隊一覧 ※本島の部隊としてのみ掲載あり
実は調べているうちに、もうひとつの謎が浮かび上がって来たので、せっかくなので披露しておきます(ある程度までは自己解決)。
第二十三連隊(第一中隊)の指揮隷属の変遷で、沖縄守備の第三十二軍、第一〇方面軍の台湾軍とあるのは判別がつくのでいいとして、最初の所属である船舶第七輸送司令部が謎なのです。ウィキペディアの船舶司令部の項目には、隷下であるはずの船舶工兵二十三連隊の名前すら掲載されていません。
それ以前に、第五船舶司令部までしか詳細項目がなく、第七船舶司令部については、わずかに沿革の項目に1945(昭和20)年1月に第7船舶輸送司令部を編成したとあるだけです。しかし、それでは船舶工兵二十三連隊の情報との時間軸が合いません。
ちなみに余談ですが、この司令部は8月の広島市への原爆投下を受けて、負傷者の救護活動を行っているようです。
先程の内閣府沖縄振興局の沖縄戦関係資料閲覧室で、「第7船舶輸送司令部沖縄支部史実資料」なるものを発見。さらに、国立公文書館アジア歴史資料センターでも、「第7船舶輸送司令部沖縄支部履歴の概要」という文章も見つけました。
これによると第7船舶輸送司令部沖縄支部は、昭和19年3月に編成完了し、4月に鹿児島から那覇に向かっています。司令本部よりも沖縄支部のが早く稼働しているということなのか、そのあたりはまだ怪しいところがありますけれど、沖縄については辻褄が合うようになりました(どうも三十二軍第十一船舶団隷下に沖縄支部は組み込まれていたようです)。
そしてこちらも沖縄戦末期となる資料末には、「兵器廠長の命により部隊は解散、本島北部の森林地区に突破を開始」という一文で終わっていました)。
結果結論として、宮古島での第一中隊についてはなにをしていたのか、現段階ではまったく判らないというのが実状です。
ただ、慰霊碑の建立されている成川は、大浦湾の西側に位置しており、すぐそばの大崎(砂山ビーチと大浦湾の間にある小さな半島)の岩礁地帯と、湾口にあるパナリ(無人の小島)に壕が見つかっており、重要港湾で空襲も多い平良港から、こちらに移っていたのでしょうか?(そもそも乗るべき船もあったかどうかも怪しい)。
情報があるようでとても少ない船舶工兵第二十三連隊第一中隊。島はまだまだ判らないことだらけです!
Posted by atalas at 12:00│Comments(1)
│んなま to んきゃーん
この記事へのコメント
はじめまして。第117回「殉国慰霊之碑」の中で慰霊碑を建てた田浦敬久の息子です。たまたま、宮古島の検索でこれが出てきました。父は陸軍でいろいろ転戦し、そのたびに配属先が変わり、昭和19年4月に特設船舶工兵第6中隊として沖縄に入っています。沖縄に着くと船舶工兵第23聯隊第1中隊と名称が変わり、本土決戦のための兵力、弾薬、食糧の輸送にあたっています。最後は宮古島への食糧輸送命令を受け、中隊の内水谷少尉以下40名が宮古島に入りました。米軍の沖縄本土上陸のあと、宮古島へも空爆がひどくなり、平良港にあった小学校も焼失したので、各小隊ごとに分散したそうです。父は分隊長をしていたそうで、度重なる空爆で食糧もつき、餓死するものが何人もでたそうで、戦後ずっと忘れられず、せめて慰霊碑建てて弔ってやりたいと思ってました。
Posted by 田浦敬三 at 2024年09月23日 13:34