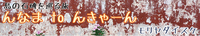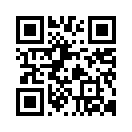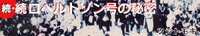2018年05月08日
第184回 「比屋地御獄案内碑」
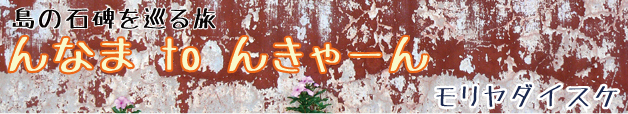
先週は平良で有名な金殿である「船立堂」の石碑を紹介しました。聡明な読者貴兄におきましては、なんとなく思わせぶりなフレーズを仕込んでおきましたので、今回はきっとここが紹介されるとお気づきになっていたのではないでしょうか。けれど、同時にここに石碑なんてあったっけ?とも思われていたのではないでしょうか?。ええ、あるんです。この比屋地御獄の入口にひっそりと石碑はあるのです。といっても、正確には伊良部村が建立した、御獄の由緒を書き記したコンクリート製の案内板なのですが、これがまたなかなかに年代物なのです。
ということで、比屋地御獄の案内碑ですが、まずこの御獄の読みから。
比屋地。苗字や地名なら「ひやぢ」でしょうが、島の読み方では「ピャーズ」となります。しかし、これは南区の伊良部側の読み方。北区の佐良浜では「コンマウキャー」と呼ばれています。こちらは牧(下牧/地名)のコン(フン≒郡/集落の意)マウキャー(前/南にある)御獄という意味なのだてそうです。同じひとつの島で異なる呼び方があるというのは、やはり基礎となる人たちの出自が異なることを示しているように感じます。特に、佐良浜地区は池間民族の系譜であり、伊良部地区は久貝を初めとする宮古のみならず、八重山や沖永良部など異邦の土地から渡って来た人たちと云われています。
碑に記されいる比屋地御獄の由来をまず、紹介しておきます。
この社に祭られている神は、赤良伴金と言う男神で五穀豊穣の神、島守の神と伝えられ、久米島から渡来してきたと言う説が有力である。祭神は赤良伴金(あからともがね)。一説には兄が“金殿”つまり鍛冶屋であって、その弟(十干十二支で、兄を“~え”、弟を“~と”と読む)なので、お伴のトモ(祭祀でもツカサなどの手伝いをする人をトモと呼ばれることがある)から、トモガネと呼ばれたとも云われています。
その頃、西暦1650年頃、宮古の処々に内乱が起り、野崎村(現在の久松)の人々が難を逃れて下牧に在る積上の地に漂着し集落を形成した。この時代に赤良兄弟が現れ、農作物の普及や農耕の技術指導を施し、島民の生活を救ったと言われている。その後、兄は(後のおもと岳の神)八重山に渡ったが、弟の伴金はこの地に残り、人々から島主に推され、豊に島を治めたので、彼の亡き後、五穀豊穣の神としてこの社に祭られた。
又、こり時代の集落が村落の発祥と云われ、島守の神として、以後、村一円の拝殿として島びとが参拝している。
施工 伊良部村役場 村長 譜久村善
奉納 (名)寿工業 代表 仲宗根太郎
役員 下地恵 普天間■
工事担当 渡久山武夫
建立年月日 昭和四十九年三月十一日
■は土に埋まっていて読めない
この兄弟は1650年代の人物とされ、久米島から渡ってきています。船立堂の逸話は神代の出来事とされていますが、「(9人)兄弟」、「久米島(を往還)」、「鍛冶屋(黒金と巻物)」という3つもキーワードが合致するのは、あまりにも偶然過ぎる気がします。
この兄弟の他にも北側(沖縄本島方面、大和の島々)からやって来た人たちの伝承は、伊良部には多くあります(1744年の話になりますが、秋田県能代の船が、宮城沖の金華山から、現在の下地島空港にあたるナガビタまで漂流した話もあるので、昔から似たような事例はいくらでもあったのではないでしょうか。大和神屋御獄/佐良浜横岳)。
【左】 冷厳な空気に包まれた木立の中にある比屋地御嶽。
【右】 マキブー≒積上の浜。遠く対岸には野崎の山並みが見えている。
そして平良の野崎村から積上(大和ブー大岩の北方に小字名があり、そこにはマキブーといわれる小さな浜がある。正面には野崎の山並みが見える)に上陸して、出耕作の畑屋(パリヤー/パリバンヤー)を経て定住してゆきます(浜の上方には、マキガーと呼ばれる降り井も残っている)。
実はこの比屋地御獄には、もうひとり祭神がいます。フカ(鮫)退治をした豊見(とぅゆん)氏です。施政者として領民の安全を守るため、ひとり鮫と戦った英雄として祀られています。名前が宮古ではよく耳にする、役職(首長)の豊見親(とぅゆみゃ)に似ているためとても紛らわしく、誤記も散見されるのですが、比屋地御嶽の入口の鳥居には「豊見親比屋地御嶽」と書かれており、字面のままイメージすると「比屋地豊見親」という人物がいたかのような誤解をしそうな気もします。神格化されたこの豊見氏が、豊見親であった記録はないようです。ただ、一世豊見氏親方を始祖とする家譜を持つ、伊安(いやす)氏を名乗る家系があります。

話が少しそれますが、この豊見氏が鮫退治に行くか行くまいかの二択を思案した伝承が伝わる、フタツガーという井戸が渡口の浜の東詰近くにあります(戦いを決意した後に、比屋地御嶽で必勝を祈願し、小舟で海に漕ぎ出して鮫と闘います)。また、後の伊安氏は伊良部に居していたといわれ(宝刀を所有する家譜的な末裔も伊良部在住)、一説ではスサビミャーカは伊安氏の墓であるとも云われています(真偽は不明)。
こうした事情を妄想して考えると、野崎から海を渡って積上に上陸し、比屋地(牧山)を経て伊良部へと移っている感じがなんとなく見えてきます。さらに、霊石のある伊良部元島や、フナハガー(久貝を元にした言葉で、後に村立てされる国仲の語源とも云われている)なども含めて夢想すると、はっきりとはしないけれど、どことなくつながりや流れが、史実と伝承と現地に痕跡として残っていて、ついつい悠久の浪漫が湧き出てくるので妄想が止まらなくなります。

【上】 カボチャ畑の中にひっそりとある、フタツガー。
【参考資料】
「綾道-伊良部島編-」 (宮古島市教育委員会 2017)
「伊良部村史」 (伊良部村役場 1978)
【関連石碑】
第109回 「清美 一九六三年三月四日」
第112回 「字佐和田村落生誕五百五十年記念之碑」
第113回 「字伊良部・仲地 村落生誕七〇〇年記念之碑」
第118回 「復帰記念事業の碑」
第150回 スペシャル企画「霊石」
第183回 「船立堂」
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│んなま to んきゃーん