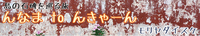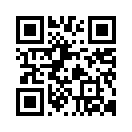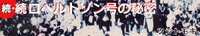2016年11月15日
第109回 「清美 一九六三年三月四日」
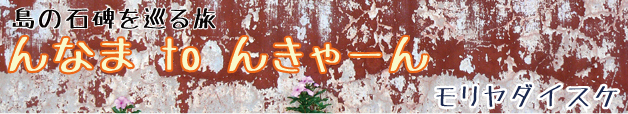
謎が謎呼ぶ「謎の石碑-未解明ファイル-」シリーズ。Part2の4回目、通算で8回目となります。未だきっちりすっきり解明に至ったものはひとつもありませんが、「わたし、気になります」的な起承転結の「起」の部分だけは提供できているのではなすかと。
さて、今回の石碑ですが、厳密には石碑とは云えないかもしれません。おそらくはこれは威部(イビ)ではないかと思われるからです。
えー、なにやら色々と説明三昧となりそうな予感がする幕開けとなりましたが、フルスロットルの妄想で進めて行きたいと思います。

まずはこの石碑のある場所から説明しておきます。場所は伊良部島の字伊良部集落の東はずれにある、伊良部の中取御嶽(ナカドゥイウタキ)の隣にある、フナハガーと呼ばれる洞泉(降り井戸)の入口の拝所のスペースの奥にあります(すでにこの説明だけで長いですね)。
拝所にはちゃんと威部(イビ)があり、香炉(器はない)もあります(龍神系≒水の神様なので、普通、火は嫌われるので香は焚きませんが、焚いている場合は水系以外の神であると云わざるを得ない)。さらに、どういうわけかペットボトルの水もお供えされています(中の水は井戸から汲んで来たものなのだろうか?)。
威部とは神様の降りる場所、拝むべき対象としてのシンボリックなもので、御嶽など御願(ウガン)する場所の真ん中に置かれる自然石などのことです(自然石でないこともある)。
「清美」の石碑はその拝所の裏手にあり、香炉も置かれています。と、いうことは威部なのでしょうか(墓とは思えないので)。
フナハガーは1430年頃に発見されたと云われており、この一帯にフナパ村、北方にウポザト村、東方にウポドウ村と三つの村があり、村建てには欠かせない水源となったといわれています(おそらくこの村々は伊良部元島のことであろうと推測します)。その後、他の地域からの移民も増え、現在の伊良部・仲地集落方面へと村が移り、1766年には仲地村が分離独立をしました。
 折角なので、井戸について、もう少し触れておきます。
折角なので、井戸について、もう少し触れておきます。御嶽の森の中にある洞泉で急峻な階段を下った奥底から豊富な水が湧き出しています。1961年頃からは近傍の伊良部製糖の工業用水として活用されています(住人の利水は上水道設備が整ったことに伴い、利用されなくなった)。そのため製糖期が近づくと井戸の清掃が行われ、拝所への祈願も行われています。
尚、井戸から工場への取水はポンプによって自動化されていますが、幾度かの改修がなされているようで、降り井戸の入口付近には古く錆びたポンプ施設(筐体のみ)や、井戸の底部には浪速ポンプの銘が入った固定金具など、近代遺構もわずかながら残されていて、マニア心をくすぐってくれます。
先にも書きましたが1430年頃にフナハガーは発見されたとありますが、現存する記録には詳細がありません。また、発音の妙から揺らぎや混同した解釈などもあるよう思われます。ここでは1727年に編纂された「雍正旧記(ようせいきゅうは)」の記述から紐解いてみることにしました。
「「雍正旧記」の伊良部村の井戸の項目には、すでに発見されているはずのフナハガーの記載がなく(神里ガーとダキフガーはある)、そのかわりに「國中川但洞川掘年数不相知(くなかかーただしどうせんつくねんすうふそうち)」と記されています。
この当時、伊良部島に記録されている村は南区の、佐和田村と伊良部村のふたつだけで(佐良浜には添村以前の旧伊良部池間邑があるものの、1903年の特別町村制成立まで公式には池間島の村の一部と扱われている)、国仲村は集落として存在していませんでした。国仲村が公の記録に出て来るのは1737年の「球陽」からで、1614年に池間島からの移民で村建てされたとあります。
しかし、1500年の仲宗根豊見親の赤蜂征伐には、「国中のままら」なる人物が帯同しているので、恐らくこの頃から畑屋(はるやー:出耕作の仮小屋)による非公式の集落が存在してたと推定されます(津波で失われたとされる下地島の木泊村なども同様)。しかし、雍正旧記にある伊良部村の國中川が、国仲村との関連を示すものでもないと思われます。
そして面白いことに、文字を読みの通りに発音すると「kunaka」となりますが、伊良部集落の発音ではカ行がハ行へと変化する子音交替が起きるため、「hunaha」という発音になり、現在の名称となるフナハガーと合致するのです。
つまり、古くから重要な井戸として雍正旧記に記載されている國中川とは、この井戸の事を示すのではないかという推理を導き出しました(井戸のみならず村建てを含め、とても伊良部島の成り立ちは複雑で興味深いのですが、長くなるのでここではやりませんが、この話も諸説のひとつと思っていただければ幸いです)。
長々と回り道をして参りましたが、本題の石碑「清美」の話に戻ります。
この井戸の神様は解説板によるとミフツヌス(美しい女神)で、集落の西にある神里(かんざと)ガーの神とともに夫婦神として厚く信仰されているそうなので、この「清美」とは清く美しい女神のことなのではないかという、あっさりやんわりと着地を試みました(ただ、神里もフナハも神の名は名乗られていない不思議)。
最後に大きな妄想を、ひとつぶっこんでおきます。
渡口の浜の入口にある乗瀬御嶽には、玉メガという女神が祀られているのですが、この女神の伝説がどことなくフナハガーの伝承に隣接しているようで気になるのです。
 昔々、ウポザト村のウプカニ(百姓にして豊見親と呼ぶ説がある)という夫婦に、玉メガというとても美しい娘がいました。玉メガが15~6歳の頃、(豆腐を作るため)乗瀬の浜へ潮汲みに行ったきり行方知らずとなります。
昔々、ウポザト村のウプカニ(百姓にして豊見親と呼ぶ説がある)という夫婦に、玉メガというとても美しい娘がいました。玉メガが15~6歳の頃、(豆腐を作るため)乗瀬の浜へ潮汲みに行ったきり行方知らずとなります。嘆き悲しみ娘を探す両親でしたがまったく見つかりません。三か月ほどたったある日、乗瀬山(現在の製糖工場から乗瀬御嶽の森)を訪れていた両親の前に、突如、玉メガが立ち現われました。
喜び駆け寄って娘を抱きしめるも、玉メガは袖を振り「我は此の島の守護神となった」といい残して、乗瀬山へと消えてしまいます。そして両親は娘の玉メガを想い、その地に乗瀬御嶽を祀ったと伝えられています。
どことなく竹取物語がモチーフにあるように感じ取れます。余談になりますが「伊良部」という言葉は、古くは“伊羅夫”と書かれ、竹取物語によると「美しく彩られた」という意味があるといいます。偶然にしては出来過ぎの関連性は妄想を大きく掻き立ててくれます。
ウポザト村の見目麗しき少女が潮汲みへ行って女神になりました。「清美」はウポザト村を含む三村の中心ともいえる美しき井戸の女神です。どちらも水に関係もしていますし、清美は神里カーと夫婦神になっています。玉メガの伝説は求婚される竹取物語がモチーフです。もしかして、玉メガは「清美」のことなのではないではないでしょうか?。
神という名の宇宙人に、玉メガ清美はキャトルミューティレーションされ、銀河の遥か彼方へ連れ去られてしまったのかもしれません。思わず荒唐無稽なSFファンタジーにしてしまいましたが、伝説の場所と伝承の地が狭い地域でどことなくクロスするというのは、あながちない話とは云えず、ついつい妄想がはかどります。
妄想のまとめ。
伊良部製糖の北側(伊良部集落側)に残る小さな森に、玉メガの父を祀ったウプカニ御嶽があります。かつてこの小さな森と乗瀬御嶽を包み込む渡口の浜の背後林は、乗瀬山としてひとつの大きな森を形成していました。親娘の御嶽は製糖工場によって分断されてしまいましたが、その製糖工場はかつての村の井戸「清美」の水を使って操業しているのでした。
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│んなま to んきゃーん