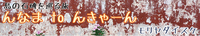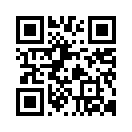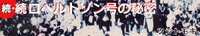2015年05月05日
第29回 「石原雅太郎氏像」

平良編の2回目は、平良町長を4期、平良市長を2期、延べ20年以上に渡って首長を務めた石原雅太郎の胸像です。
胸像としては宮古高校に移転した際に取り上げた盛島明長に続く二例目となりますが、奇しくもふたりはほぼ同時期に活動した盟友であり、近代宮古の礎を築いた政治家として知られています。
とても興味深い経歴を持つ石原雅太郎を中心に、ざっくりとまとめてみようとしました。とっても、興奮のあまり上手くまとまりませんでしたが・・・。

雅太郎は1881(明治14)年5月15日に平良に生まれます。後に宮古王と呼ばれた盛島明長も前年の1880年に、下地間切洲鎌村で誕生しています。さらに面白いことに雅太郎と同じ年の3月10日に、城辺の比嘉で比嘉財定が生まれています(後の東大法学部を卒業した人物。早生まれなので学齢は明長と同じ計算になる)。
1902(明治35)年に沖縄師範学校を卒業すると、雅太郎は宮古郡宮古高等小学校へ赴任します(尚、現在の平良第一小学校の旧称は宮古島高等小学校であり、明治39年4月から明治41年3月の間だけだったことから、記録違いと思われます)。
翌、1903年には多良間尋常小学校へ、また1906(明治39)年には伊良部尋常高等小学校へ転任しますが、その年の5月には病気による休職を申し出ています。
ところが雅太郎は宮古を離れ、東京へと向うのでした。人頭税が廃止されてわずか4年という時代にです。そして怒濤の雅太郎のトーキョーライフが始まります。
1907(明治40)年1月 東京府豊玉郡渋谷尋常高等小学校(該当する同名校は不明)に代用教員として採用。
1907(明治40)年5月 私立日本大学法律科専門部に入学。
1908(明治41)年1月 東京市京橋区文海尋常高等小学校(現在の新富町駅前付近)に代用教員として採用。
1909(明治42)年4月 東京市京橋高等小学校に採用(文海小と同じ?)。
1910(明治43)年2月 私立日本大学法律科専門部を自主退学。
若干、採用された校名が怪しく、完全には再現しきれないのですが、教育者として雅太郎は邁進して行くかと思いきや、なんと今度は北海道へと飛びます。
1911(明治44)年2月18日、小樽高等商業学校(現・小樽商科大学)に職員(書記)として赴くのです。感の良い方はすでにお気づきかと思いますが、この小樽商科はロシアからやって来た不遇の言語学者、ニコライ・ネフスキーが教鞭を取った学校として知られており(在籍していますのは1919年/大正8年)、もしもここでふたりが出逢っていたら、ネフスキーの宮古訪島は早まっていたかもしれません。
誇大妄想は置いておくとして、小樽へとやって来た雅太郎は、なんと一年もたたないうちに職を辞して小樽を去ってしまいます(12/5依願退職)。宮古生まれの雅太郎にとって、北海道が寒かったという訳ではないようで、どうやら当時の平良高等小学校長であった立津春方に、同校の教頭職を乞われて宮古へと戻ったらしいのです。
ちなみに、この立津春方は後に初の公選村長で当選し、第八代平良村長(1920~1921)を務めます。どことなく雅太郎が次に向かう方向性が垣間見れた気がします。
1932(昭和7)年、雅太郎は満を持して第六代の平良町長に就任します。そこから第七代、第八代と町長を三期連続で務めます(1932~1939)。任期中の1936(昭和11)年には、博愛記念碑建立60周年が行われ、雅太郎は町長として出席し、町長として歓迎宴も開いています。
ここで少し興味深かったのは、当時の新聞に掲載されていた60周年の祝賀広告に、雅太郎と並んで「代議士・盛島明長」の名前があったこと。
そしてもうひとり、比嘉長間耕地整理組合長の肩書で瑞慶覧朝牛の名前を見つけたことでした(以前、取り上げた瑞福隧道を推進した、後の城辺町長)。他にも色々と気になる名前などがありましたが、それはまた別のお話…。
1944(昭和19)年、雅太郎は実に四期目となる第十代平良町長(1944~1945)に就任し、任期中に終戦を迎えます。そして敗戦国となった日本は、統治していた台湾を放棄(中華民国へ)、沖縄はアメリカ軍による軍政下となり、宮古から台湾へ疎開した人たちの引き上げは遅々として進まない中、栄丸遭難事件が発生します(11月)。
「戦時中、自分の命令で彼らを台湾に疎開させたのだ。疎開させて放任する訳には行かない」として、雅太郎は翌12月には町長職を辞し、陣頭指揮をすべく台湾へと渡り引き揚げ事業に尽力します。
1949(昭和24)年、平良市の第3代平良市長となり、雅太郎は首長として再び戻って来ます(最終的に続く第4代までの2期を務めた)。そして雅太郎の代名詞ともいえる、電気の安定供給、上水道の近代化、港湾の拡張整備の「平良三大事業」に着手します。この政策によって現在の平良の基盤が作られるのでした。
 1975(昭和50)年、石原雅太郎、94歳で没。平良市初の名誉市民の称号が贈られます。尚、名誉平市民には雅太郎の他に、博愛記念碑関連で幾度も名前が登場する育英の父こと下地玄信と、那覇出身の具志堅宗精(宮古警察署長から宮古民政府知事、退職後は実業界入し、赤マルソウやオリオンビールを創業)。そして元岡山県津山市長である額田雄治郎の三名に贈られています。
1975(昭和50)年、石原雅太郎、94歳で没。平良市初の名誉市民の称号が贈られます。尚、名誉平市民には雅太郎の他に、博愛記念碑関連で幾度も名前が登場する育英の父こと下地玄信と、那覇出身の具志堅宗精(宮古警察署長から宮古民政府知事、退職後は実業界入し、赤マルソウやオリオンビールを創業)。そして元岡山県津山市長である額田雄治郎の三名に贈られています。ただひとりの非県系人である元津山市長の額田雄治郎は、次週お送りする予定の胸像シリーズ第三弾に繋がってゆきます。
石原雅太郎の逸話には興味が尽きません。実は「石原雅太郎伝」(1963年刊行)という本が存在するのですが、図書館にすら蔵書がなく読むことが出来ません。もしもこれを読むことが出来れば、さらに雅太郎に迫ることが出来るのですが、それがかなえられないのが残念でなりません。
※胸像台座の説明文~画像をクリックで大きくなります(1963年3月17日建立)
連載企画 「んなま to んきゃーん」
なにかを記念したり、祈念したり、顕彰したり、感謝したりしている記念碑(石碑)。宮古島の各地にはそうした碑が無数に建立されています。
それはかつて、その地でなにかがあったことを記憶し、未来へ語り継ぐために、先人の叡智とともに記録されたモノリス。
そんな物言わぬ碑を通して今と昔を結び、島の歴史を紐解くきっかけになればとの思いから生まれた、島の碑-いしぶみ-を巡る連載企画です。
※毎週火曜更新予定 [モリヤダイスケ]
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│んなま to んきゃーん