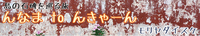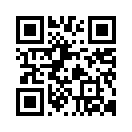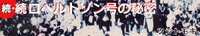2014年12月02日
第7回 「博愛-公爵近衛文麿書-」
ドイツ商船ロベルトソン号遭難に始まる博愛記念碑の物語は、さまざまなヒストリーを紡ぎ続けながら現代まで繋がっています。そんな博愛関連の碑シリーズ第2弾です。
カママ嶺公園の宮古総合実業高校側の麓。うっそうと茂った林の中に建つ大きな石碑です。
近年、新宮古病院の建設に伴う公園駐車場入口の変更工事によって道路の線形が改良され、バン工房アダナス(みやこ学園アダナス分場。ここは旧・博愛スーパーだった)側からも石碑が見えるようになりました。

石碑の裏に書かれている碑文。
近年の研究成果から、遭難者救助の真相や船長のドイツ未帰国譚、「博愛」の時局ごとの変遷など、これまで知られていた歴史の真相が紐解かれ、非常に興味深い事象となっています。
碑文の中にも紹介されている下地玄信(1894-1984)は、以前、第2回で紹介した博愛記念碑のレプリカや、ドイツ村の遭難の地の碑にも関係してくる人物なのですが、奇しくもこの碑が建立されたのと同じ頃の1984(昭和59)年5月23日に亡くなっています。
また仄聞したところでは、近衛文麿が揮毫した「博愛」の文字は、1936(昭和11年)の博愛記念碑60周年で建立された、ドイツ村にある遭難の地の碑(こちらも文麿揮毫とある)とともに記されたもので、永らく書(掛け軸か?)のまま保管されているばずだったが、石碑建立の際に紛失が発覚し、やむを得ず書を撮影してあった写真から起したらしいとのこと…。
ちなみに、近衛文麿は3度も内閣総理大臣になっているが、第一次内閣は1937年組閣なので、この書を書いた頃はまだ総理ではなかったであろうと推測されます。
近衛文麿
1891(明治24)年-1945(昭和20)年 政治家・公爵。東京生まれ。
五摂家の筆頭の家柄で、1937年に45歳7ヶ月という伊藤博文に次ぐ若さで、内閣総理大臣となり第一次近衛内閣を組閣するも、盧溝橋事件に始まる日中戦争の和平交渉に失敗。1940年の第二次近衛内閣では、新体制運動が陸軍に利用され大政翼賛会が成立。また日独伊三国同盟を締結して「南進」政策を取る。1941年7月に対米調整するため総辞職し、第三次近衛内閣を組閣したが、東條英機の対米主戦論に破れて総辞職した。終戦後の1945(昭和20)年12月。A級戦犯として極東国際軍事裁判で裁かれることになるが、巣鴨拘置所に出頭命令に応じず青酸カリを服毒して自殺。没年54歳2ヶ月は歴代総理大臣でもっとも若く、死因が自殺なのも唯一である。
カママ嶺公園の宮古総合実業高校側の麓。うっそうと茂った林の中に建つ大きな石碑です。
近年、新宮古病院の建設に伴う公園駐車場入口の変更工事によって道路の線形が改良され、バン工房アダナス(みやこ学園アダナス分場。ここは旧・博愛スーパーだった)側からも石碑が見えるようになりました。

石碑の裏に書かれている碑文。
碑文
この「博愛」の碑銘は、近衛文麿公爵の書である。
明治6年6月17日(旧暦)に宮古島の南方沖合いで台風に遭遇したドイツ商船、エル・ロベルトソン号の遭難者8人を救助し献身的な介護のうえ、無事、ドイツに帰国させた。
この宮古の人々の崇高な博愛精神に近衛公が感激し、博愛の書を記され、宮古出身の下地玄信にくだされたのを同氏から宮古へ寄贈されたものである。
この栄誉を記念するとともに、この行為が博愛の象徴のひとつとして、後世に伝えられることを願い、この碑を建立するものである。
記、建立費用の大半は、「育英の父」と称される下地玄信先生から寄せられたものである。
昭和59年5月吉日
博愛記念碑建立期成会
近年の研究成果から、遭難者救助の真相や船長のドイツ未帰国譚、「博愛」の時局ごとの変遷など、これまで知られていた歴史の真相が紐解かれ、非常に興味深い事象となっています。
碑文の中にも紹介されている下地玄信(1894-1984)は、以前、第2回で紹介した博愛記念碑のレプリカや、ドイツ村の遭難の地の碑にも関係してくる人物なのですが、奇しくもこの碑が建立されたのと同じ頃の1984(昭和59)年5月23日に亡くなっています。
また仄聞したところでは、近衛文麿が揮毫した「博愛」の文字は、1936(昭和11年)の博愛記念碑60周年で建立された、ドイツ村にある遭難の地の碑(こちらも文麿揮毫とある)とともに記されたもので、永らく書(掛け軸か?)のまま保管されているばずだったが、石碑建立の際に紛失が発覚し、やむを得ず書を撮影してあった写真から起したらしいとのこと…。
ちなみに、近衛文麿は3度も内閣総理大臣になっているが、第一次内閣は1937年組閣なので、この書を書いた頃はまだ総理ではなかったであろうと推測されます。
近衛文麿
1891(明治24)年-1945(昭和20)年 政治家・公爵。東京生まれ。
五摂家の筆頭の家柄で、1937年に45歳7ヶ月という伊藤博文に次ぐ若さで、内閣総理大臣となり第一次近衛内閣を組閣するも、盧溝橋事件に始まる日中戦争の和平交渉に失敗。1940年の第二次近衛内閣では、新体制運動が陸軍に利用され大政翼賛会が成立。また日独伊三国同盟を締結して「南進」政策を取る。1941年7月に対米調整するため総辞職し、第三次近衛内閣を組閣したが、東條英機の対米主戦論に破れて総辞職した。終戦後の1945(昭和20)年12月。A級戦犯として極東国際軍事裁判で裁かれることになるが、巣鴨拘置所に出頭命令に応じず青酸カリを服毒して自殺。没年54歳2ヶ月は歴代総理大臣でもっとも若く、死因が自殺なのも唯一である。
連載企画 「んなま to んきゃーん」
なにかを記念したり、祈念したり、顕彰したり、感謝したりしている記念碑(石碑)。宮古島の各地にはそうした碑が無数に建立されています。
それはかつて、その地でなにかがあったことを記憶し、未来へ語り継ぐために、先人の叡智とともに記録されたモノリス。
そんな物言わぬ碑を通して今と昔を結び、島の歴史を紐解くきっかけになればとの思いから生まれた、島の碑-いしぶみ-を巡る連載企画です。
※毎週火曜更新予定 [モリヤダイスケ]
Posted by atalas at 14:53│Comments(0)
│んなま to んきゃーん