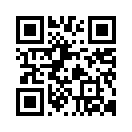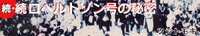2015年10月02日
金曜特集 「いよいよ復刻!『宮古教育』『教育時報』のご紹介」

[編集部からお知らせ]
本来なら10月第1週金曜日は「みやこのこよみ」の掲載日ですが、ご本人も含め一家で熱発をされたため、残念ながら休載とさせていただきます。尚、ご家族の体調が復旧し、安定してからの復帰となりますのでご了承ください。
ということで、「月イチ金曜コラム」。今週はいつにも増してスペシャルなゲストライターさんの緊急登場となりました。括目せよ!

ゲストライターの高橋順子です。私が携わっている2015年の秋から発売予定のとある復刻版シリーズに、宮古の資料も収録されることになりました。とても貴重なものだと思いますので、少しご紹介したいと思います。
どのようなシリーズかと言いますと、敗戦から琉球政府が出来るまでの1945年~52年の間に、奄美、沖縄、宮古、八重山の各群島にそれぞれ出来た教職員団体の機関誌を、全部復刻して世に出そうというものです。
たった7年間の資料ですが、戦前の教育史と、琉球政府が出来てからの教育史の間をつなぐ懸け橋になっている重要な部分です。また大変な混乱期に、各群島がどのような「戦後」を歩もうと立ち上がったのか、それぞれの特徴が良く出ています。
そもそも今まで、読もうと思っても、どの群島の団体がどんな雑誌を出していたのか、何号から何号まであるのか、どこの図書館にどんな資料が所蔵されているのかなど、わからないことだらけで、興味を持っても自分で調べるには大変な労力がかかっていました。
それが復刻版で一度に読めるようになること、復刻版を機に初めて発見された資料が収録されることなどから、関連領域の研究が進む礎になるのではないかなと思っています。
さて、宮古群島に目を移してみますと、その教職員団体は、1946年にいち早く「組合」としての組織作りを試みたり、独自に日本国憲法を「密輸」して他群島に先駆けて1948年に教育基本法を制定したりと、戦後沖縄教育史においても注目される歴史を歩んできました。
その団体機関誌である『宮古教育』と『教育時報』が、今回の復刻で初めて広く公開されることになります。収録される計23号分は、1947年9月から1952年1月発行、2~8ページの新聞形式。うち1号分が個人所蔵、他が宮古島市史編さん室所蔵のため一般公開されてこなかったからです。『平良市史』第5巻に部分的な翻刻がある限りです。
なお、後継誌『宮古教育時報』の一部は沖縄県立図書館、沖縄県公文書館、宮古島市立図書館等に所蔵されています。
ではその時期の宮古の教職員団体と、機関誌の変遷を概略してみましょう。
1946年9月、戦前から続いた宮古郡教育部会(池村恒章会長)を解消し、教育の民主化と教師の生活の安定、政治参加を求めて、宮古教員組合が結成されました。
委員長は砂川恵敷(平良第一小学校長、以下の肩書はいずれも当時)。この時期に教職員団体を「組合」として組織したことは、宮古群島の大きな特徴のひとつと言えます。しかし、米軍や内部対立等の影響を受け、10ヶ月弱で解散となりました。
次に、1947年7月、「会員間並びに社会の教育文化の進展に貢献する」ことを目的として、宮古教育会を結成しました。会長は池村恵信(平良第一小学校長)。そして同年9月、「群下400」の「教育者相互の切磋琢磨と郷土文化建設への提携の実を挙ぐる」ため、機関誌として『宮古教育』が創刊されました。現在までに唯一発見されている創刊号を見てみると、B5判8ページ、月1回発行非売品となっています。20号程度まで発行されたそうです。
その後、1949年5月、宮古教育会から分かれて高校教育会が結成されました。会長は垣花恵昌(宮古高校長)。宮古教育会は、池村恵信(平良南中学校長)の会長続投を決定し、1950年4月、「(450名)会員の研鑚は勿論、広く社会、経済、政治、宗教、文芸などの諸問題をも取扱い皆さんと共に子供達の幸福のためにそして文化宮古建設のために力強く再出発する」ため、誌名を『教育時報』と改めて、機関誌の体制を一新しました。
サイズを大きくし、月刊から週刊に発行回数を増やし、購読料を月15円としました。専任編集者を置く体制をとって、1951年新年号までを花城朝勇が担当。その後、平良南中学校の宮国泰昌や本村玄典らが兼任で担当。紙面では社会情勢のほか、教員の生活安定、PTA、新教育としつけ、教育委員制度、育英会制度、独立校舎の必要性等が訴えられるなど、会の方針が表れています。
1950年9月実施の宮古群島知事選挙ののち、文教部長が砂川恵敷から垣花恵昌に引き継がれ、また、校長の池村恵信(平良南中学校)が退職することになりました。垣花は高校教育会長、池村は宮古教育会長だったため、それぞれの組織の体制を新たにする必要が生じます。
そこで翌1951年4月、宮古教育会の会長に与那覇春吉(平良第一小学校長)が選出され、5月、高校教育会が合流しひとつの組織に戻ります。
『教育時報』でも専任編集者が変わり、同年6月から1953年3月まで、譜久村寛仁が担当。週刊から月6回、その後隔日刊へと発行回数を増やし、購読料も月30円としました。1952年7月、宮古教育会は、会則を一部変更するかたちで宮古教職員会と改称し、沖縄教職員会の地区組織化に備えていくことになります。
『宮古教育』と『教育時報』は、新聞形式で最終的には隔日刊、会員に限定しない広い読者を対象としているところに特徴があると言えます。また、1945年から1952年までの間に、言論の自由を求めて新聞や文芸誌が続々と創刊され、本誌もその一翼を担いました。それらが休刊、廃刊となっていく中で、復帰まで継続的に発行されたという意味では、宮古戦後史を映す大変貴重な資料群であるとも言えましょう。教員たちはこれらを学校単位ではなく、殆ど全員が個人で講読していたそうです。
米軍と宮古行政による検閲、また政治の影響を受けながらも、生活不安と社会的地位の低さに悩む教員たちを励まし、軍国主義と封建的イデオロギーから解放されたことを喜び、デモクラシーに基礎を置く新教育を創造していこうとする熱意が伝わってきます。
今後、欠号が発見され、組織動向や教材研究等の情報がより明らかになっていくことを期待したいと思っています。
最後に、宮古の資料には、ペンネームがたくさん使用されています。もしご存知の方がいらしたら、教えて頂けたら嬉しいです(敬称略)。
【参考文献】
・沖縄県教職員組合宮古支部『宮古教職員会20年史』 1973年
・平良市史編さん委員会『平良市史』第5巻、第1巻通史編2、平良市役所、1976年、1981年など。
■この記事は『沖縄タイムス』2015年9月14日に掲載された高橋執筆記事が元になっています。この前後に他群島の記事も掲載されていますので、合わせてお読みいただければ幸いです。
■復刻版『占領下の奄美・琉球における教員団体関係史集成(仮題)』計7巻(不二出版)
高橋順子 (社会学、沖縄研究)、埼玉県生まれ。日本女子大学助教
主著に『沖縄<復帰>の構造―ナショナル・アイデンティティの編成過程』新宿書房、2011年など。
最近は、沖縄教育史、女性の復帰運動、チャイナ陣地、沖縄平和学習、ナショナリズム等その他諸々について取り組んでいます。
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│金曜特集 特別編



![[新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019 [新春特番] ATALASネットワークpresents 新春放談2019](http://img01.ti-da.net/usr/a/t/a/atalas/2019sp-001-s.jpg)