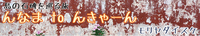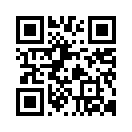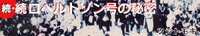2018年04月24日
第182回 「迎御嶽大明神」
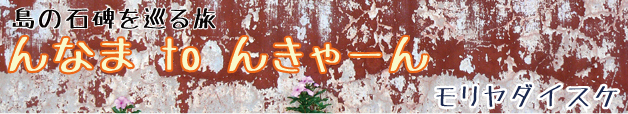
「平和の犬川」「観音堂経塚」「宮古熊野三所権現鎮座之地」と、はからずも漲水界隈三部作が続いたので、気をよくしてひとつだけ延長戦をお届けしてみることにしました。今回ご紹介する石碑は、宮古神社の社殿の裏手。北側(図北)にひっそりと佇む、赤い鳥居が建つ迎御嶽の敷地にあります。石碑に記された碑文は、なかなか渋くて今風な表現をするなら、クールともいえるのですが、石碑そのものには見かけほどの“強さ”がありません。
この場合の“強さ”は石碑の内容と云うことで、簡単に申し上げてしまうと、こちらの石碑はよくある御嶽の改修記念碑にすぎません。
石碑に記されている情報によると、1959年2月1日に多くの寄付金を集めて建立されています。戦後、復帰前という時代なので寄付額は「弗」の字をあてたドル表記になっています。
ちなみに筆頭寄付者は富山兄弟一同とあり、2位以下を大きく引き離す100ドルを寄付しています(2位で30ドルなので圧倒的)。どのような人物なのかはこれだけ判りませんが、豊見山のように三文字姓ではないことから、内地人もしくは寄留民の系統ではないかと思われます。また、ずらりと並んだ寄付者の名前を見ると、苗字はさまざまですが、名乗り頭に「恵(惠)」の字が多いことから、白川氏の系統が関係しているようです。
実はこの御嶽、頼みの平良市史御嶽編には掲載されていません(注①)。なので、いわれや詳細を知ることが出来ないのですが、佇まいなどから考察して妄想力を全開にして、トンデモで身勝手に紐解いてみたいと思います(もしも、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、なにとぞご教示下さい)。
まず、石碑にも書かれている「迎御嶽大明神」。御嶽は過去に神社化への道をたどり、数多くの御嶽に鳥居が建てられてきましたが、大明神ってのは元々は仏教用語とされ、いわば明治維新以前の神仏習合(しんぶつしゅうごう)の名残ともいえる言葉なのだそうな(ただし、鹿島大明神や稲荷大明神など大明神号を使用する神社もある)。また、赤い鳥居の赤(正確には朱)も、神仏習合の時代に仏教から導入された色だとか(確かに寺院は朱塗りが多い)、だいぶチャンプルー感が高まってまいりました。
面白い解釈のひとつに四象(四神霊獣)との関係がありました。この御嶽にある鳥居は南を向いており、南の四象は朱雀なので、その赤(朱)に由来しているというもの。この解釈は方角的には当てはまっていますが、宮古神社の二の鳥居は同じく南向き(厳密にいえば、どちらも南南東)ですが白木のままです。
もっとも、宮古神社と違い、迎御嶽は鳥居の正面に祠(社殿)がなく、正面には今回紹介している石碑が建立されています。祠は鳥居に対して東に90度曲がったところにあるのです。この点から類推すると敷地の関係と神社化のための鳥居の建立を両立させた結果、このような位置関係になったようにも思われます。またしてもチャンブルー感が薫って来ました。
そんな祠の中にはご神体と云うべきなのか、三種の神器とされる八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、草那芸之大刀(くさなぎのたち/草薙剣の旧名)をなぞらえたような、神鏡がひとつと、水晶玉(真贋は?)が安置されています。御嶽にしてはどことなく本格的に神社率が高めな感じがします。
しかし、ここで石碑にの裏面に寄付者とともに記されていた、重要なカードを切ってみたいと思います。
それは
「大黒出雲之神 天乃金殿」
と、ふたつの神の名が記されているのです。
書き方がちょっと気になれますが、大黒出雲之神は大黒様は、大国主命のことなので出雲大社の神様です。三種の神器ってのは、天照大御神のお話なので伊勢神宮系ですよね。朱雀はともかく神仏習合だのなんだの語りましたが、チャンプルー感が暴走し始めている気がしてなりません。
つたない知識ではありますが、ちなみに宮古神社は熊野三神系(と三豊見親神)なので、確かアマテラス寄りです。もっとも、沖縄の神社は「琉球八社」を見てもアマテラス側なので、さすが南国の太陽神はキョーレツです(それは陽射しだ)。とはいえ、琉球にとって内地式の神社神道は、新しい概念でしかないので、この辺はチャンプルーというより、テーゲーなのかもしれません。
ま、こうしてあれやこれやと色々ながめてみると、まさにスピリチアルなんてのは「鰯の頭も信心から」ってとこなのかもしれませんね。
そうそう、大黒出雲之神と並んで書かれていた地元代表の「天乃金殿」ですが、単に金殿といわれると鍛冶屋神のこと(金属を扱うのでカネ≒金)。これはつまるところ農具を作り直す人が神格化されたもので、廻り廻って農耕の神のことであり、転じて繁栄をもたらす恵みの神様とされています。ちょっと盛りすぎなような気もしますが、“天の”って修飾されるってことは、もしかしたら天照(アマテラス)のことだったりするのかもしれませんね(大局的な時系列からすると、まったく違うのであとづけ設定ならありそう)。さすが八百万も神様がいるので、妄想考察すると面白いですね。
そこでさらに思ったのですが、この迎御嶽を神社化せしめるのであれば、単にヤマトガム(大和神)を祭神に足すことで方向性が出る気がするのですが、出雲や伊勢の神がより具体的な形で登場するあたりは、内地人らしき人がメイン(寄付金)になって改修したからなのでしようか。
また、特定の家(門中?)に繋がる人たちだけが拝んでいる様子も、どことなく感じられる気もする点に加え、平良市史の御嶽編には御嶽でありながら一切取り上げられていない。このあたりを妄想たくましく考えると、もしかすると、ここは御嶽を神社化したのではなく、私設の神社(戦時中に一部の部隊が独自に拠り所としての神社を建てたという流れもある)を、御嶽化したのではないかという大胆な仮説をたててみました。身勝手なこの説、皆さんの印象はいかがでしょうか?。
【関連石碑】
第179回 「平和の犬川」
第180回 「観音堂経塚」
第181回 「宮古熊野三所権現鎮座之地」
【20180427改訂】
初稿で『平良市史御嶽編には掲載されていません』と書いてしましたが、改めて御嶽編を見直したら、西仲宗根の項目に「ンカイ御嶽」として掲載されていました(P252)。実は、この御嶽の東角は、東仲宗根と西仲宗根と西里の3字の境界になっていたのでした。勝手な思い込みで、東仲宗根と西里しかチェックをしていませんでした(謝)。
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│んなま to んきゃーん