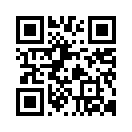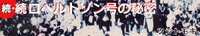2018年03月09日
30冊目 「あの瞬間ぼくは振り子の季節に入った」

東京に届いた本を、東京の友人に見せたら、まず「名前が読めない」と言った。
「にかどりまさきさん」と答えた。
そう。荷川取雅樹さんの本が出た。
作者いわく、小説風エッセイ。
「あの瞬間ぼくは振り子の季節に入った」
というタイトルだ。
本の内容は、宮古の70年代から90年代の空気をまとっている。
タイトルを見ると、笑える人には笑え、懐かしい人には懐かしいものだと思う。これから宮古に旅する人には、ぜひ読んでほしい。
なぜなら、私が思うに、今は面影だけが残っているからだ。
記憶1
屋上の龍/地下の亀
墓の上の子供
琉映館3D映画事件
素晴らしい日曜日
記憶2
パイナガマ・ヒーロー
心、ぽとり
午前二時のフースバル
小宇宙のバースデーケーキ
世界が愛で殺される前に
記憶3
マクラム通りから下地線へ、ぐるりと
警察・ジプシー・チキンカツ
「アミが、無免許でパクられたってよ」
前夜のジョン・レノン
記憶4
ぼくは雪を見たことがある
ちょっとめんどくさいけど、読んでほしい。
わたしたちの宮古がどれだけ変わったか、ということについてです。「離島研究 IV, 第 4 巻」に「1984年に10万人を超えた」とある。1984年(昭和59)といえば東急リゾートだ。
私は、中2で、荷川取さんは高3。これは、小説を読めばわかるのだけど、荷川取さんが事故にあった前後ではないかと思う。
ちなみに、今は宮古島だけで観光客数は100万人を越えようとしている。
今、ネットで確実にわかる資料としては、昭和61年 が一番古い。59,580人だそうだ。6万人の地元民と、10万人の観光客。
今は、平成30年3月1日現在で、55,372人だ。5.5万人に100万人。そして、宮古に住む人は誰もが知っている通り、住民票を移していない人が山ほどいる。私の推測だと常時、3,000~6,000人はいるのではないかと思う。
何が言いたいかというと、多分、当時、島には「人づて」というローカルニュースであふれていた。
そして遠い東京からやってくるサブカルな香りに、刺激を受けた市内の一部の子どもたちがいた。ギャングのように、街中を闊歩してはいたけど、私たちは因習のなかに確実に生きていた。その現実と妄想を邪魔するほどの島にあふれる人たちはいなかった。
島独特のメンタリティが色濃くどの作品にも現われている。それが、私たちの世代ではないかと思う。復帰後は、統計はないが、多分観光客は数1,000人単位だったと思う。それが倍々ゲームで増えていった。
その初期段階で、私たちは生まれ、子どもとして暴れ、若者として謳歌した。荷川取さんを一緒にしては悪いけど。
本の紹介としては、かなり不足気味だとは思いますが、ここで勘弁してほしい。なぜなら、私には物語ではなく、あまりにリアルだからだ。紹介というよりネタバラシをしてしまいそうだからだ。
そして、この本を本当に読んで欲しいと思う理由がある。
昨今の地元民、移住者、観光客、宮古出身者が宮古に戻った時に連れ来る宮古2世たち、そういうさまざまなひとが、荷川取さんが描く街に同じように入り乱れている。そして、摩擦がある。
文化背景の違い、と言ってしまえば、そうなのだけど「なぜ宮古の人とぶつかるのか、そして、さらになぜ絆が深まるのか、もしくは断絶してしまうのか」。その答えがあるような気がするからだ。
宮古の人に知り合ったら、読んでほしい。
宮古の人を好きになったら、さらに読んでほしい。
宮古の人と恋愛したら、もっと読んでほしい。
宮古の人と別れそうになったら、何度か読んでほしい。
宮古の精神性って、こういうところにあるかもしれない、と感じてほしい。
自分で書いていて、わけがわからないが、宮古のマグネティックな力は、どの作品にも現われている。
文:宮国優子
[書籍データ]
あの瞬間、ぼくは振り子の季節に入った
著 者 荷川取雅樹
発 行 ボーダーインク
発行日 2018年2月20日
ISBN 978-4-89982-335-3
関連書籍
12冊目 「マクラム通りから下地線へ、ぐるりと」(2016年9月9日)
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│島の本棚