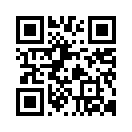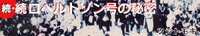2017年08月11日
23冊目 「キジムナーkids」

8月です。皆さんはどんな夏休みを過ごされるでしょうか。
さて今月の1冊は、上原正三著『キジムナーkids』です。
本書は、上原氏の自伝的小説で、沖縄版『スタンド・バイ・ミー』と謳われています。
著者の上原正三さんは、ウルトラマンの企画脚本で有名な金城哲夫氏らともに円谷プロダクションから活躍したシナリオライターです。ウルトラマンシリーズの他、東映の『がんばれ!!ロボコン』『秘密戦隊ゴレンジャー』『宇宙刑事ギャバン』など、あの懐かしいアニメや特撮を手掛けてきた方なのです。

表紙を開けると
太平洋戦争の戦中戦後を
共に生き抜いた
キジムナーkidsへ
と書かれています。
上原さんは1937年生まれ。小説の主人公ハナーは、小学校2年生で熊本に疎開し、4年生になって故郷沖縄へ引き上げてきます。
物語は、ハナー、ハブジロー、ポーポー、ベーグァ、サンデー等、小学生の子供達を主人公に、戦争中や戦後の沖縄での暮らしが描かれます。小さな体と純粋な心で、一生懸命に過酷な時代を生き抜く沖縄の子供達の姿に涙してしまいます。また、そんな子供たちを取り巻く大人の姿にも、戦争の残した深い傷とそれを乗り越えようとする生き様があります。米軍のトラックドライバーのアマワリ、九州から来たヨカ先生、パンパン(娼婦)のハル、戦争で気が狂ったと思われているフリムン軍曹・・・。激しい戦争を生き残ったハナーの父親は、ハナーに「幽霊と友だちになりなさい」と言います。“戦場では、みんな幽霊だ。幽霊にならなきゃ生きていけない。だから死んでも幽霊になって出てくる。幽霊も仲間なんだ。だから怖くない。怖くないんだ。”死んだから幽霊になるのではなく、戦争にいくということは、既にもう幽霊なのだという、この言葉の重さが心に残ります。
だから、時に当時の沖縄に漂う死の気配に怯え、マブヤーマブヤーと唱えるハナーは、“早く逃げろと命じるボクと、たとえ亡霊だろうと、相手が何を言いたいのか、なぜこんなことをしているのか。聞いてあげるべきだと主張するボクの二人がいる”と感じるのです。
他の子どもたちのエピソードにしても、戦争さえなければこんなに辛い想いをしなかっただろうに、しかしある意味では子どもの普遍性を持って、明るくしぶとく邁進する姿勢にこちらが勇気づけられます。
著者があとがきで、こう述べています。
それはおそらく、子供は透視能力を身につけているからだと思う。その魔法の目で、一人ひとりがはるか彼方に色とりどりの光を見つけ、その光を掴むために走り出していた。戦争に生き残った子供たちは、戦後の混乱にも、進駐軍の圧力にも潰されることはなかった。そんな子供たちを軸に戦中戦後の沖縄を書こうと思った。
このような子ども時代を過ごした上原さんだからこそ、ウルトラマンやロボコンなどの不朽の名作を生み出せたのですね。
また、この本にはウチナーグチ(方言)がたくさん出てきます。上原さんは、あえてウチナーグチを多用したそうです。
方言は、その土地で生まれ育ったもの同士で交わす言語である。方言には、その土地の海や山の情景、土や風の匂いまでも思い出させてくれる力がある。だから、お国なまりを耳にしただけで、標準語の拘束から解放され、ホッと癒やされる。(あとがきより)
各ページの下部にはウチナーグチの日本語訳が記されているので、読みやすく、ウチナーグチの勉強にもなります。
もし、私が学生なら間違いなく読書感想文に選ぶ1冊です。
いえいえ、大人になってからでも読んでほしい名著だと思います。この夏一番のおすすめです!。
“二〇一七年、ウチナー戦(イクサ)から七十二年目の初夏に――上原正三”
※著者・上原正三さんと評論家・切通理作さんの『キジムナーkids』刊行記念対談(前後編)が見られます!→コチラ
〔書籍データ〕
キジムナーkids
著者 /上原正三
発行/現代書館
発売日 / 2017/6/23
ISBN /978-4-7684-5804-4
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│島の本棚