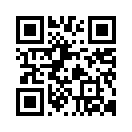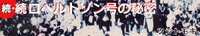2019年05月17日
第13回「下川凹天の撮影技師 柴田勝の巻 その1」

まずは、毎度おなじみ。裏座から宮国でございます。宮古ももう梅雨の時期ですね。
この時期の宮古といえば「湿気」。6〜8月の平均湿度は、83%だそうです。数字にされると、衝撃が走ります。

島にいる頃、私は、特段不具合は感じなかったのですが、それは子どもだったからかもしれません。あと、太陽光線が半端ないので、それどころじゃなかったとも言えます。
島の子どもたちのアイラインをしたような縁取りのある目元や眉毛を見ていると、湿度&太陽光線対策として発達したのだろうな、と思うのです。それは、どこか物悲しく懐かしい横顔に私の目には写ります。

先日、生前の凹天を知るふたりに会いました。写真は、その帰りに行った喫茶店です。このことは、いずれここでもご紹介しようとは思います。
実は、私が心に残った言葉があります。おしゃべりの間だったので、はっきりとした文言はおぼえていませんが、要するに凹天が「ちょっと怖かった」そうです。「いかつい」というか「濃い」というような文脈でした。
当時のエリートは、ツルッとした美青年(宮古でいうところの好男子、笑)のイメージがあったのでしょうが、凹天はそう見えなかったってことなのでしょう。芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ)、太宰治(おざわ おさむ)、中原中也(なかはら ちゅうや)、萩原朔太郎(おぎわら さくたろう)とか、かなりツルッとしたイケメンな気がします。
凹天を血脈で考えると、親は鹿児島と熊本なので、そんなに濃いこともないような気がしますが、東京のパリッとしたエリート層に投げ込まれると、褐色の肌に彫りの深い顔は土着的に見えたのかもしれません。
最初の妻、たま子との結婚の新聞記事も「美女と野獣」ばりのことを書かれていた記憶があります。新聞記事にまでなるってことは一応有名人というか芸能人に近く、エグザイル並みの野生感があったのでしょうか。私には、野生の男というと、それがいくら作りものであったとしても、エグザイルくらいしか思い浮かびません・・・。貧困ですいません。
あ!同時代だと、大杉栄(おおすぎ さかえ)がそれにあたる野生派イケメンだったのかもしれません。凹天はイケメンじゃなかったですが・・・。

こんにちは。一番座より片岡慎泰です。
今回は、凹天が日本で初めてのアニメーターとなった時期、アニメーション映画制作を支えたとされる撮影技師の柴田勝(しばた まさる)を取り上げます。
1897年、大森家の5人兄弟の3男として、東京府北豊島郡日暮里村(現・東京都荒川区日暮里)で誕生した柴田勝。子どもの頃から、淺草六区に通って、映画ばかりを観ている少年でした。当時の映画は大人5銭、子ども3銭。10銭もっていくと映画を2本観て、お汁粉を食べて、観音様にお賽銭を1銭あげたと回想しています。子どもの頃よく通ったのは、吉澤商店、エム・パテー商店、横田商會、福寶堂の映画でした。好きだったのは、吉澤商店系で、日本初の常設館である淺草電氣館。後の1912年、この4社はトラストで、日本活動フイルム株式會社を経て、元号が大正となった同年に日本活動冩眞株式會社、つまり日活と改称します。
田中純一郎著『日本映畫史 第一巻』(齋藤書店、1948年)によると、元々、電氣館は、電気仕掛けの器具やエックス光線の実験を見せて、電気の知識を普及する傍ら、見世物料として、料金を取る見世物小屋でした。それが、経営不振になり、1903年、活動寫眞の常設館の日本第1号となったのです。
当時は、見物人は腰掛もない土間に立たされて、下駄ばきで、人の肩越しに映画を観ていたとのこと。遊山気分で豪奢な芝居見物とは大違いでした。田中純一郎は、各地にできた常設館に、歌舞伎を始めとする芝居役者連が、下駄ばきで見学される活動寫眞に出るのは、舞台役者の名折れだと述べたということも記しています。


柴田勝は、映画好きが昂じて、1916年、天活(天然色活動寫眞株式會社)の撮影技師になりました。すぐに枝正義郎(えだまさ よしろう)の助手になる幸運に恵まれます。
ところで、まず初めに、ここ数年、凹天が再注目を浴びる理由となったきっかけとなった出来事とともに、今回はそこでの記述に関し、封切日の検証をしてみようと考えます。
一昨年の2017年、日本の映画アニメーション誕生100周年ということで、渡辺泰(わたなべ やすし)をリーダーとするアニメNEXT_100というプロジェクトが組まれ、われらが凹天の劇場公開された初作品について、新説が出されました。

http://anime100.jp/series.html


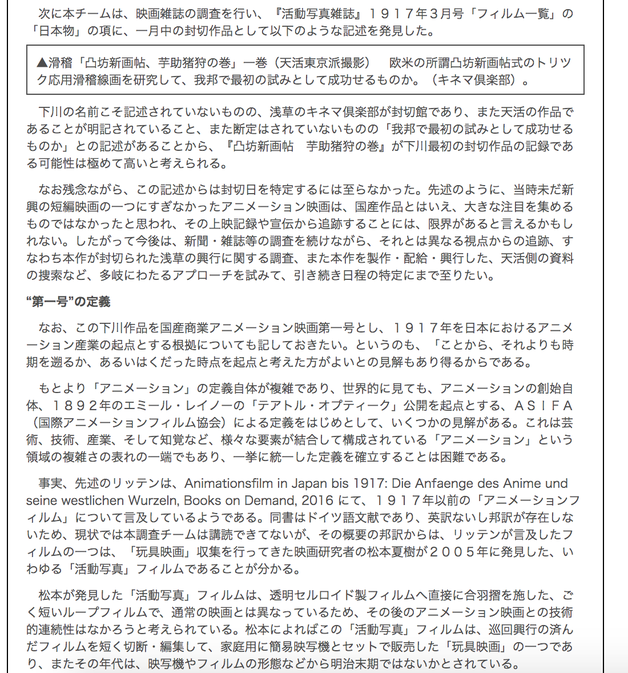

アニメNEXT_100では封切日が特定できないとありますが、絞り込むことは可能です。1916年12月29日付『東京朝日新聞』には、シネマ倶樂部の広告として、新春興行は1月3日からとあります。
秋田孝宏著『『コマ』から『フィルム』へ マンガとマンガ映画』(NTT出版、2005年)には「日本で最初に輸入されたアニメーション映画は、1914年イギリスアームスロング社の作品」。上演は淺草帝國館。その時初めて「凸坊新画帖」という名が付けられ、その後大正から昭和初期にかけて、アニメーション映画は「凸坊新画帖(帳)」と呼ばれたとあります。
また、田中純一郎著『日本映画発達史II 無声からトーキーへ』(中公文庫、1976年)によれば、当時アニメーション映画を意味する言葉には「線画」、コマ落としで撮影するので「トリック(特殊技術)」、その他「線画喜劇」、「カートンコメディ」もありました。
この広告(先述の1916年12月29日付『東京朝日新聞』のシネマ倶樂部の広告)には、その言葉が見当たりません。
しかし、翌日の1916年12月30日付『東京朝日新聞』には、「春の與業物案内」に、シ子マ倶樂部のところで、予告として『プロデア姉妹篇 黒團長』、『活劇 毒彈』とならび『女装のチヤツプリン』、そして『凸坊』が登場しています。
そして、1917年1月3日付『東京朝日新聞』には、シネマ倶樂部のところで「天活直営館として開会せり」とあります。すなわち、この日が、商業的日本アニメーション映画の記念すべき公開初日である可能性大なのです。1916年から1917年当時、凹天も天活に勤めていました。

その後、1917年1月6日付『東京朝日新聞』には、シネマ倶樂部におけるメディアに向けた上映記録が載っています。これは、その日から始まるシネマ倶樂部の新春興業第2弾に向けてのものでした。再び、裏座から宮国です。
「天活會社シ子マ倶樂部に上演する金剛星の試演を看たがホンのまだ六十番の内の第一二篇五巻だけの口切だが大物としての價値は十分に現れてゐた殊に題材に取入れたジプシイ種族の風俗がちよい/\出て來るのにも興味がある。鉄假面五番も水滸伝的で一寸面白い添物には例のチヤプリンとデコ坊があつた」。
津堅信之著『日本アニメーションの力 85年の歴史を貫く2つの軸』(NTT出版、2004年)では、当時日本アニメーションの第1作と考えられていた凹天の『芋川椋三 玄關番の卷』について、試作品だったかもしれないとの仮説を提示していますが、その根拠が示されていません。勝手な憶測ではありますが、「試演」という言葉に反応したように読むことができます。試演とは、さしずめ現在の試写会といったところでしょうか。
この時代あたりから、映画界は、「試写会」の重要性に気づき始めます。当時は、ラジオもテレビ、ましてやインターネットもない頃です。もっとも、試写会が全盛になるのは、かなり後のことになります。時代は戦後になりますが、種村季弘(たねむら すえひろ)が、映画評論事情を振り返って、こう語っています。
「昔は映画にしても演劇にしても、試写、試演に批評家が来ると、帰りに金一封をヒュッと渡した(笑)。新聞社でもらう原稿料の十倍くらいくれたんだね。ぼくらの頃はさすがにそれはなかったけど。でもそれは書式が決まってて、『その通りに書きなさい』ってことなのね。官庁の文章みたいになってて、それに署名するための欄が空いてるだけで、それに、いまどきなら十万円なら十万円って札束が乗っかってるのが御用批評家の世界なんですよ」。
シネマ倶樂部の後、『凸坊』が有樂座で上映された記録が残っています。シネマ倶樂部も有樂座も、当時は天活の直営館でした。1917年1月13日付『讀賣新聞』によると、有樂座は1月10日から始まったとあります。仮に、先ほど述べた1月3日に上映されていなくとも、現段階では判明しませんが、少なくとも「試演」のあった6日以前には、シネマ倶樂部で上映されていたのです。
先に引用した1917年1月6日付『東京朝日新聞』にある「例のチヤプリンとデコ坊があつた」という記述と合わせて、とりあえず、このブログでは、われらが凹天作のアニメーション映画初上映は、1月3日から5日に絞られることをここで記しておきます。
柴田勝に話を戻します。凹天と出会った後、柴田勝は「異例のバッテキ」で念願の映画監督になります。第1作は横須賀相模新聞社の観桜会でした。その後も枝正義郎の助手を続けながら、映画監督として作品を作ります。しかし、翌1918年に、神田錦輝館、現像工場が全焼。天活をライバル視していた小林商會も同年に倒産。小林商會が引き抜いた幸内純一(こういち じゅんいち)が制作した『塙凹内名刀之巻刀(なまくら刀)』は、2007年に偶然発見され、日本アニメーション映画創成期の貴重な資料になっています。
また、柴田勝はメモ魔だったこともあって、映画界創成期などのことについて、大量に日記やメモ、文章を残してあるのは特記すべき点でしょう。凹天とのことを織り交ぜつつ、インタビューに答えた文章も残っています。現像、撮影から「劇に移ったのはいつ?」とインタビュアーに聞かれて、1984年こう回想しています。
「やっぱり六年ですね。最初は実写とか、漫画、下川凹天という、亡くなりましたけど、これが最初に白墨で黒板へかくんですよ。それをそのまんま写すんですからね。直光線ですよ。だから晴れたときに回しはじめると、曇ったら駄目なんですよ。レンズの絞りを変えることは出来ませんから。一定の絞りでやらないと、絵が大きくなったり小さくなったりしますからね。だから曇るとやめて、ちょうど前に錦輝館という映画館がありましたので、そこへ映画を見に行くんですよ。それで晴れたなと思うとまた帰ってきて・・・・・・。そういうような、一本撮るのに随分時間がかかった。それで、こんなのではしょうがないというので、今度は紙に書きまして台の上にカメラを乗せ、ライトを両脇につけて、手で回しました。これはライトでしたから一定していますから早かったですね」。
この大正六年、すなわち柴田勝による1917年の回顧には、いろいろな資料を突き合わせて考える必要があるのですが、次回以降ということで。
一番座からは以上です。
宮古はその頃どうだったかというと、立津春方(たてつ しゅんぽう)と盛島明長(もりしま めいちょう)の時代だったのではないでしょうか。
1917年は、医師であった盛島明長が県会議員に。後には副議長、議長を歴任。その2年前の1915年は、慶世村恒任(きよむら こうにん)の『宮古朝日新聞』と、垣花恒栄(かきはな こうえい)の『宮古公論』という新聞が初めて発行されました。
1920年の宮古初の衆議院議員選挙で、新聞は大きな役割を果たします。立津春方サイドは『宮古新報』と、盛島明長サイドは『宮古時報』でした。
2010年9月19日付『宮古毎日新聞』の創刊55周年記念特集の「 宮古の新聞の興亡を回顧する」で、仲宗根將二(なかそね まさじ)がこう書いています。
「歴史家の稲村賢敷は、後年、『新聞といえば個人の私行をあばくものとして敬遠されたものであった』と記している」(『宮古島庶民史』三一書房、1957年)
マスメディアの発露が政治とからみ、近代化とともに本格的に人々の生活が複雑になっていったように思えます。
また、現在とリンクしているのは、宮古馬について。
1917年は、種牡馬を除く3歳以上の牡馬の去勢を定めた馬匹去勢法が施行。度重なる陳情で、その5年後にあたる1922年に適用区域から外されたので、宮古では8,597頭のうち99%が在来馬として残ったそうです。
沖縄本島は、半数以上が改良馬となったのに比べると、陳情のかいがあったのでしょう。
その詳しい理由は、今は知るよしもありませんが、外部からの働きかけが激しくなり、宮古の人にとっては激動の時代の幕開けだったのでしょう。それは、もちろん、日本も同じだっただろうとは思うのです。
東京では、紙メディアから、映像メディアに移っていく時代に、宮古は紙メディアがようやく始まりました。紙、音、映像、どちらも一方向というのが共通点です。ですが、現在は、SNSを含め双方向になっています。テクノロジーの発達を見ると、さらに加速化してくのでしょう。
この100年を振り返ると、メディアにおいては、加速度的な世紀。そして、それは続くのでしょう。だからこそ立ち止まり、こうして先人たちのエッセンスに目も耳も傾けたいと思うのです。
そもそもメディア(media)という言葉の語源は、ラテン語のmedium(メディウム)から派生した言葉です。中間にあるもの、間に取り入って媒介するものという意味があります。
なので「媒体」「仲介者」「霊媒」が意味になります。「霊媒」とは、あの世とこの世の「神の声を媒介する人」という意味のようです。人類の歴史を考えると、その意味が続いた期間のほうが長かったにちがいありません。多分、カンカカリャーやユタはメディアそのものです。そして、それは双方向。
時代がぐるっとまわって、メディアの古い形に会うために、宮古島に人が押し寄せる。なんだか面白い現象だな、と感じています。
さて、私たちは、先人たちの声のひとつひとつをこうしてとりあげます。こうして現代のウェブ「メディア」にのせておくことは、どんな意味があるかわかりませんが、それは、記録であり、未来への贈り物にはちがいありません。
【主な登場人物の簡単な略歴】
大杉栄(おおすぎ さかえ)1885年~1923年
社会運動家、作家、翻訳家。愛媛県那珂郡丸亀(現・香川県丸亀市)生まれ。東京外国語学校(現・東京外国語大学)卒。学生時代に、堺利彦、幸徳秋水を知る。エスペラント語学校を開く。1906年、電車焼き討ち事件に連座して、初めての逮捕。1908年、屋上演説事件で、再び逮捕。1910年の大逆事件の際には、幸徳秋水との関係を刑務所で探られるが、この時は、検挙を免れる。1914年頃、ダーウィンの『種の起源』を翻訳、出版する。社会主義からアナキズムの立場を徐々に鮮明にしていく。1916年、伊藤野絵との恋愛も始まり、翌年、長女の魔子誕生。1920年、コミンテルンから呼ばれ、中華民国の上海で開かれた社会主義者の集会に参加。1921年1月、コミンテルンからの資金でアナ・ボル(アナキスト・ボルシェヴィキ)共同の機関紙としての『労働運動』(第2次)を刊行。しかし、2月に腸チフスを悪化させ入院。12月にはアナキストだけで『労働運動』(第3次)を復刊させる。1923年、上海からフランス船籍の船に乗車し、中華民国経由で中国人に偽装してフランスに向かった。アジアでのアナキストの連合も意図し、上海、フランスで中国のアナキストらと会談を重ねる。2月13日にマルセイユ着、大会がたびたび延期されフランスから国境を越えるのも困難になる中、大杉はパリ近郊のサン・ドニのメーデーで演説を行い、警察に逮捕され、ラ・サンテ監獄に送られる。日本の大杉栄と判明、裁判後に強制退去となる。在フランス日本領事館の手配でマルセイユから箱根丸にて日本へ。同年、滞仏中から滞在記が発表され、後に『日本脱出記』としてまとめられる。また、かつて豊多摩刑務所収監中に日本で初翻訳した『ファーブル昆虫記』が『昆虫記』の名で出版。東京に落ち着き、8月末にアナキストの連合を意図して集まりを開くが、進展を図る前に関東大震災に遭遇。9月16日、柏木の自宅近くから伊藤野枝らとともに憲兵に連行され、殺害される。
枝正義郎(えだまさ よしろう)1888年~1944年
映画監督、撮影技師。広島県佐伯郡玖島村(現・廿日市市玖島)生まれ。1908年、日本で最初に映画の興行に着手したといわれる吉澤商店に入り、目黒行人坂撮影所で千葉吉蔵に師事、シゴキ抜かれ現像と撮影技術を学ぶ。その後、天活(天然色活動寫眞株式會社)に入り、撮影技師、監督となる。ここでは澤村四郎五郎、市川莚十郎の旧劇映画を撮影。天活の技術部長となった枝正は、安易に量産されるようになった映画界の風潮を嫌い、また国産でも外国映画に負けない良質な映画を製作しようと様々な技術開発を進める。1917年に撮った連続活劇『西遊記』は、長尺の2000~3000フィートの作品で、四郎五郎の孫悟空が雲に乗って飛ぶところを移動撮影でとらえたりする工夫がこらされ、枝正の創意が示されていた。カメラ技巧には早くから一見識を持ち、枝正の撮影した作品は、他社作品に比べ遥かに場面転換が多く、他にも大写し、絞りこみなどを各作品に多用、また現場焼付も流麗に仕上げられ、トリックの名手として世に知られた。またこの頃、当時おもちゃ工場で働いていた円谷英二と偶然、飛鳥山の花見の席で出会う。日本映画の底上げをしようと考えていた枝正にとって現行のスタッフでは物足らず、日本ではまだ珍しい飛行機の知識を持ち、玩具で新しいアイデアですぐに成功する円谷は、枝正にとって魅力があった。1918年、天活日暮里で旧劇撮影の傍ら、製作・脚本・演出・撮影もすべて枝正の手によって行われた監督第1作『哀の曲』を撮る。この映画は、海外にも通用するような作品を目指して製作された意欲的な恋愛劇として注目された。1921年、撮影技術研究のためアメリカに渡るが、帰国すると天活は国活に買収されていた。技師長となった枝正は、ここでも幻想的な時代劇『幽魂の焚く炎』を撮り野心作と高い評価を得た。1923年、関東大震災で国活も崩壊。翌年松竹下加茂に移り、これ以降は監督に専念。1927年、阪妻プロへ移り、ダイナミックな演出で阪妻の代表作となった『坂本竜馬』などを発表。翌年東亜キネマに監督部長として迎えられるが退社して独立。1934年、得意のトリック撮影を生かして自主制作を続けた。以降は大都映画技術部総務、大映多摩川撮影所庶務課長を歴任。結核のため死去。
渡辺泰(わたなべ やすし)1934年~2020年
アニメーション研究者。大阪市生まれ。高校1年生の時、学校の団体鑑賞でロードショーのディズニー長編アニメーション『白雪姫』を見て感動。以来、世界のアニメーションの歴史研究を開始。高校卒業後、毎日新聞大阪本社で36年間、新聞制作に従事。山口旦訓、プラネット映画資料図書館、フィルムコレクターの杉本五郎の協力を得て、『日本アニメーション映画史』(有文社、1977年)を上梓。ついで89年『劇場アニメ70年史』(共著、アニメージュ編集部編、徳間書店)を出版。以降、非常勤で大学アニメーション学部の「アニメーション概論」で世界のアニメーションの歴史を教える。98年3月から竹内オサム氏編集の『ビランジ』で「戦後劇場アニメ公開史」連載。また2010年3月より文生書院刊の「『キネマ旬報』昭和前期 復刻版」の総目次集に「日本で上映された外国アニメの歴史」連載。2014年、第18回文化庁メディア芸術祭功労章受章。特にディズニーを中心としたアニメーションの歴史を研究課題とする。2017年に、山口旦訓に絶縁の手紙を送る。近親者のみで葬儀が執り行われる。喪主は、長男の渡辺聡。
種村季弘(たねむら すえひろ)1933年~2004年
独文学者、評論家。東京市豊島区池袋に生まれ。東京都立北園高等学校を経て、東京大学文学部卒。財団法人言語文化研究所附属東京日本語学校(現・学校法人長沼スクール東京日本語学校)に就職。1958年、光文社に入社。『女性自身』編集部を経て、書籍部で単行本の編集にあたり、手塚治虫、田宮虎彦、結城昌治、梶山季之たちを担当。1960年、光文社を退社し、フリーとなる。1964年、駒澤大学専任講師。1965年、グスタフ・ルネ・ホッケ『迷宮としての世界』を矢川澄子と共訳、三島由紀夫から絶賛推薦され出版した。1968年、東京都立大学助教授となる。1968年に初の単行本である評論集『怪物のユートピア』を刊行。1969年の『ナンセンス詩人の肖像』では、ルイス・キャロル、エドワード・リア、モルゲンシュテルン、ハンス・アルプらの生涯と作品を紹介。ザッヘル=マゾッホなど多くのドイツ語圏の作家を翻訳、紹介した。澁澤龍彦や唐十郎らと共に1960年代 - 1970年代の、アングラ文化を代表する存在となる。1971年、都立大学を退職。西ドイツ滞在を経て、1981年、國學院大學教授。受賞多数。2001年、國學院大學を退職。胃癌のため、静岡県内の病院で死去。
幸内純一(こううち じゅんいち)1886年~1970年
漫画家、アニメーション監督。岡山県生まれ。凹天、北山清太郎とならぶ「日本初のアニメーション作家」のひとり。岡山県での足跡は不明。両親と弟、姪と上京する。父の名は、幸内久太郎。荒畑寒村によれば、父の職業はかざり職人の親方。元々、熱心な仏教徒だったが、片山潜と知り合い、社会主義者となる。日本社会党の評議員にも選ばれている。最初は画家を目指しており、水彩画家の三宅克己(みやけ かつみ)、次いで太平洋画会の研究所で学ぶ。そこで、紹介で漫画雑誌『東京パック』(第一次)の同人北澤楽天の門下生として政治漫画を描くようになる。1912年、大杉栄と荒畑寒村が共同発行した思想文芸誌『近代思想』の巻頭挿絵を描く。凹天の処女作『ポンチ肖像』に岡本一平とともに序言を書いている。1917年、小林商會からアニメーション『塙凹内名刀之巻(なまくら刀)』を前川千帆と製作。これは、現存する最古の作品である。続いて、同年には『茶目坊 空気銃の巻』、『塙凹内 かっぱまつり』の2作品を発表するが、小林商會の経営難でアニメーション製作を断念。しかし、『活動之世界』に載った『塙凹内名刀之巻(なまくら刀)』についての評論は、これも本格的なアニメ評として日本最古とされる。1918年に小林商会が経営難で映画製作を断念。1918年、『東京毎夕新聞』に入社し、漫画家に戻る。その後、1923年に「スミカズ映画創作社」を設立すると、『人気の焦点に立てる後藤新平』(1924年スミカズ映画創作社)を皮切りに『ちょん切れ蛇』など10作品を発表。その時の弟子に、大藤信郎がいる。二足のわらじの時代をへて、最終的には政治漫画家として多数の作品を残した。凹天と最後に会ったのは、記録上では、前川千帆の葬式後、直会の時だった。老衰のため、自宅で死去。
立津春方(たてつ しゅんぽう)1870年~1943年
政治家、教育者、ジャーナリスト。砂川間切西里村(現・宮古島市西里)生まれ。立津姓は、多良間島の名族である平良土原氏の長男系統に由来する。宮古出身で、初めて断髪をしたことで知られる。1893年、沖縄県立師範学校卒。その後、宮古教育界に大きな足跡を残す。その時期の石原雅太郎、盛島明長との争いは、宮古における教育界だけに留まらず、新聞界、果ては政界にいたるまで大きな影響を及ぼした。1920年、宮古初の公選選挙で当選し、第8代平良村長となる。
盛島明長(もりしま めいちょう)1880年~1941年
政治家、医師、教育者、ジャーナリスト。宮古郡下地村(現在の宮古島市)生まれ。宮古への愛はすさまじく、「宮古王」と呼ばれた。詳しくは、「 んなま to んきゃーん 」第5回「盛島明長像」及び「 んなま to んきゃーん 」第21回「盛島明長生誕之地」。
慶世村恒任(きよむら こうにん)1891年~1929年
郷土史家。砂川間切下里村大原(現・宮古島市下里)生まれ。代用教員をつとめるかたわら研究し、1927年、宮古初めての通史といわれる『宮古史傳』を刊行した。詳しくは、「 んなま to んきゃーん 」第1回「宮古研究乃父 慶世村恒任之碑」。
仲宗根將二(なかそね まさじ)1935年~
郷土史家。沖繩縣平良市西里(現・沖縄県宮古島市西里)生まれ。1944年鹿児島縣姶良郡加治木町(現・鹿児島県姶良市加治木町)に疎開。鶴丸高校を経て、1956年宮古島に帰郷。宮古毎日新聞、日刊沖縄新聞、宮古教育委員会で、市史編纂や文化保護事業に従事。他方で、平良市役所税務課にも勤務。他にも宮古の所属機関多数。前宮古島市史編さん委員会会長。『宮古風土記』(ひるぎ社、1988年)他、著作、論文多数。宮古の生き字引と呼ばれる。『軌跡』(2016年)で、東恩納寛惇賞受賞。現在も精力的に、宮古の歴史や文化財に関する研究や発表を行っている。
【2020/09/09現在】
Posted by atalas at 18:13│Comments(0)
│Ecce HECO.(エッケヘコ)