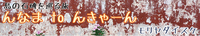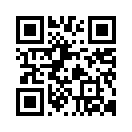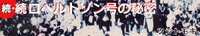2015年01月20日
第14回 「ドイツ皇帝博愛記念碑」
予想外の延長戦へ突入するなどして、「ドイツ商船ロベルトソン号遭難に始まる博愛記念碑の物語」のシリーズは、通算で10回目を数えましたが、いよいよ今回が大トリ。本家本元の博愛記念碑のご紹介です。
云わずと知れた、ドイツ帝国初代皇帝ウィルヘルム一世(ヴィルヘルム・フリードリヒ・ルートヴィヒ・フォン・プロイセン)から贈られた記念碑です。少しだけ歴史を紐解いてみると、プロイセン王であったこの皇帝はドイツ統一(1871年)をなしとげたばかりで、極東の島国・日本の片隅にある小さな島(といっても、当時はまだ琉球国だった)とはいえ、実際に軍艦を派遣するなど、国際情勢の中の日本との関係を含み、国威を示したかったのではないかと思われます(尚、ロベルトソン号の船長エドワルドは、ドイツ帝国の南西太平洋域の植民地化にも深く関係している。しかもその地域の大半は、後に南洋として日本の信託統治領となる)。
また、極東の新興国であった日本も、1871(明治4)年に台湾でおきた宮古島島民遭難事件から、征台の役(牡丹社事件1874年)へと向う、激しい国際情勢の流れの中にあり、年表に記されている歴史上の出来事が、とても複雑に影響し合っていて、宮古島的な部分だけを見ても興味深い時代となっていますが、それはまた別のお話。

碑文の解説(県教育委員会)



【左】カママ嶺にある100周年の際に作られた、レプリカの碑との厚みの違いがとてもよく判ります。
【中】県の碑、市の碑に加え、各年代の行政が思い思いに案内を建立している上に、記念物が記念碑であるだけにとても混沌です(右端は海亀剥製工場の永久看板~工場はありません)。
【右】60周年の式典が執り行われた頃には、石碑は境内にあったといわれている金剛禅寺の跡を示す碑(現在は野原に移転している)。
※画像をクリックすると大きくなります。
「ドイツ商船ロベルトソン号遭難に始まる博愛記念碑の物語」シリーズで紹介した碑一覧
第2回 「ドイツ皇帝博愛記念碑 レプリカ」
第7回 「博愛-公爵近衛文麿書-」
第8回 「独逸商船遭難の地-公爵近衛文麿-」
第9回 「独逸商船遭難救助 佐良浜漁師顕彰碑」
第10回 「博愛」@宮古島市役所上野庁舎
第11回 「ドイツ商船乗組員救助者 顕彰碑」
第12回 「博愛之塔」
第13回 「博愛の心-創立百周年記念碑」
云わずと知れた、ドイツ帝国初代皇帝ウィルヘルム一世(ヴィルヘルム・フリードリヒ・ルートヴィヒ・フォン・プロイセン)から贈られた記念碑です。少しだけ歴史を紐解いてみると、プロイセン王であったこの皇帝はドイツ統一(1871年)をなしとげたばかりで、極東の島国・日本の片隅にある小さな島(といっても、当時はまだ琉球国だった)とはいえ、実際に軍艦を派遣するなど、国際情勢の中の日本との関係を含み、国威を示したかったのではないかと思われます(尚、ロベルトソン号の船長エドワルドは、ドイツ帝国の南西太平洋域の植民地化にも深く関係している。しかもその地域の大半は、後に南洋として日本の信託統治領となる)。
また、極東の新興国であった日本も、1871(明治4)年に台湾でおきた宮古島島民遭難事件から、征台の役(牡丹社事件1874年)へと向う、激しい国際情勢の流れの中にあり、年表に記されている歴史上の出来事が、とても複雑に影響し合っていて、宮古島的な部分だけを見ても興味深い時代となっていますが、それはまた別のお話。

碑文の解説(県教育委員会)
県指定史跡 ドイツ皇帝博愛記念碑
指定年月日 1956年2月22日
指定地 平良市字西里182-5
1873(明治6)年7月。ドイツ商船ロベルトソン号は中国福州から濠州へ向かう途中に台風にあって漂流。宮国沖合で座礁難波した。宮国の人びとは夜通しかがり火をたいて励まし、荒天をついて乗組員8人を救助した後に34日間にわたって手厚くもてなし、島役人たちは官船を与えて帰国させた。
のちにこのことを知った当時のドイツ皇帝ウィルヘルム一世は宮古島の人々にの勇気と博愛の精神をたたえ、1876(明治9)年3月、軍艦チクローブ号を派遣して記念碑を建立したという。
碑文は表がドイツ文と漢文、裏は漢文で記されている。この一帯は親越とよばれ、漲水港をみおろす丘の中腹に建てられた大理石の碑は、当時は漲水港のはるか沖からも夕日にかがやいてよく見えたという。
なお、この地域を無断で現状変更することは、禁じられています。
文化財を大切にしよう!1996年2月
沖縄県教育委員会
平良市教育委員会
※すぐ隣に英文でも書かれています。



【左】カママ嶺にある100周年の際に作られた、レプリカの碑との厚みの違いがとてもよく判ります。
【中】県の碑、市の碑に加え、各年代の行政が思い思いに案内を建立している上に、記念物が記念碑であるだけにとても混沌です(右端は海亀剥製工場の永久看板~工場はありません)。
【右】60周年の式典が執り行われた頃には、石碑は境内にあったといわれている金剛禅寺の跡を示す碑(現在は野原に移転している)。
※画像をクリックすると大きくなります。
「ドイツ商船ロベルトソン号遭難に始まる博愛記念碑の物語」シリーズで紹介した碑一覧
第2回 「ドイツ皇帝博愛記念碑 レプリカ」
第7回 「博愛-公爵近衛文麿書-」
第8回 「独逸商船遭難の地-公爵近衛文麿-」
第9回 「独逸商船遭難救助 佐良浜漁師顕彰碑」
第10回 「博愛」@宮古島市役所上野庁舎
第11回 「ドイツ商船乗組員救助者 顕彰碑」
第12回 「博愛之塔」
第13回 「博愛の心-創立百周年記念碑」
「ドイツ皇帝博愛記念碑」も平良北コースに掲載されています。
宮古島市neo歴史文化ロード 「綾道-あやんつ-」
宮古島市教育委員会公認、スマートフォン向けアプリ(Apple/Android版)
連載企画 「んなま to んきゃーん」
なにかを記念したり、祈念したり、顕彰したり、感謝したりしている記念碑(石碑)。宮古島の各地にはそうした碑が無数に建立されています。
それはかつて、その地でなにかがあったことを記憶し、未来へ語り継ぐために、先人の叡智とともに記録されたモノリス。
そんな物言わぬ碑を通して今と昔を結び、島の歴史を紐解くきっかけになればとの思いから生まれた、島の碑-いしぶみ-を巡る連載企画です。
※毎週火曜更新予定 [モリヤダイスケ]
Posted by atalas at 12:00│Comments(0)
│んなま to んきゃーん